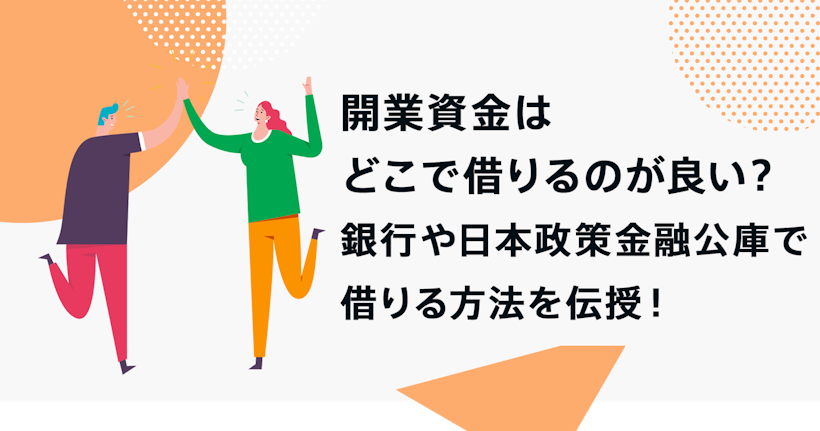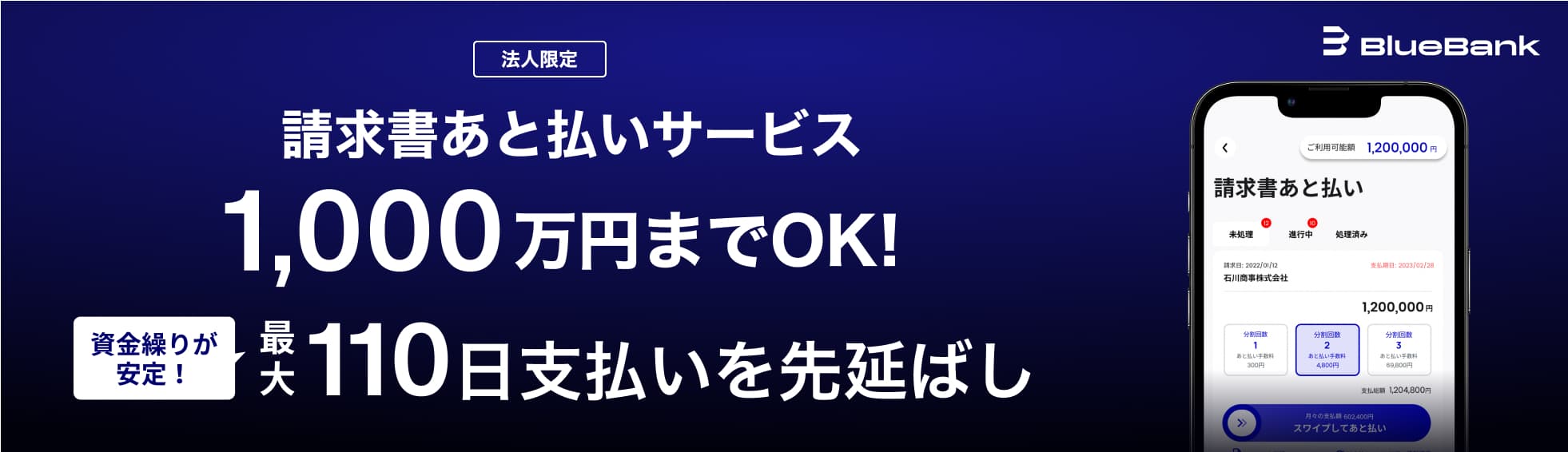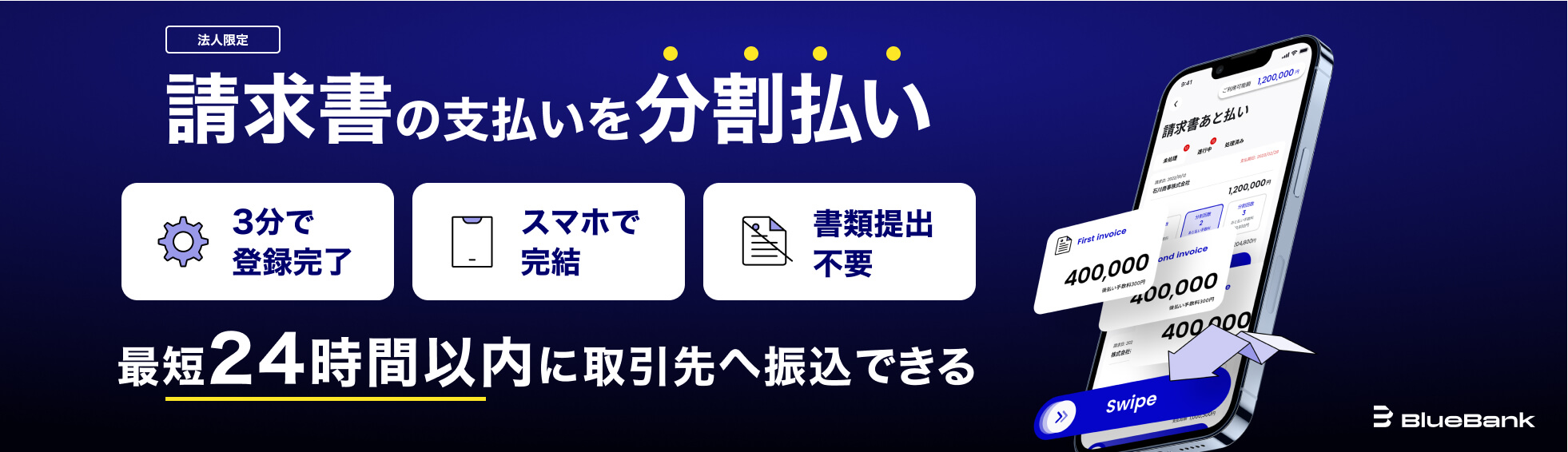開業資金の融資が借りやすいのはどこ?
創業者の方が借り入れをする方法としては、政府系金融機関や銀行などの融資がありますが、それぞれで使いやすさが違います。
また、どれを選ぶかで利用できる額や金利、その他の条件も異なります。
そのため、はじめに金融機関の特徴や融資制度をシッカリと把握したうえで申込むことが、上手な借り入れの第一歩といえます。
銀行は借入実績重視!開業資金に係る融資は借りにくい
借り入れといえば、すぐに銀行を思い浮かべるほど、銀行融資は最もポピュラーな資金調達方法の一つです。
しかし、銀行は「過去の実績を見て貸す」という傾向が強いため、資金力や実績の少ない創業者がすぐに有利な条件で借りられることはほぼありません。
銀行が行う融資には、主に「プロパー融資」と「信用保証協会の保証付き融資」(制度融資を含む)の2種類があります。
「プロパー融資」とは、銀行が他の保証機関を利用せず、独自の責任にもとづいて貸し出す融資のことをいいます。この場合は、企業の倒産や返済の不能といったリスクを自ら負わなければならないため、審査もかなり厳しいものとなります。
一方、「信用保証協会の保証付き融資」は、国の機関である信用保証協会が公的な保証人となるため、最小限のリスクで貸出しをすることができます。そのため、創業者であっても、低金利、無担保・無保証で融資を受けることが可能です。
このように、銀行からの融資は身近な方法の一つですが、創業者の方は、信用保証協会を利用しない限り、有利な条件で融資を受けるのはかなり難しいといえます。
日本政策金融公庫は起業による雇用創出に熱心、開業資金融資は受けやすい
銀行の中でも、創業者の方にとって、より融資をうけやすいのが日本政策金融公庫です。
日本政策金融公庫は、国が設立した中小企業を対象とした金融機関で、創業者であっても、長期にわたって低金利で高額の借り入れをすることができます。
また、日本政策金融公庫では、雇用の創出に力を入れていることから、開業後に社員やパートなどの雇用を計画している場合には、さらに融資をうけやすくなります。
とくに、創業者向けの融資メニューである「新創業融資制度」には、次のような特徴があります。
・ 開業後2期までの創業者が利用できる。
・ 融資上限額が3,000万円と大きい。
・ 事業計画書の提出と一定の要件を満たすだけで借り入れができる。
・ 無担保、無保証での借り入れができる。
・ 一定の方の申込みの場合は、創業にかかる経費の1/10の自己資金が必要。
このように新創業融資制度には、他の金融機関にはない特徴があるため、創業者の方が利用する融資としては、もっともおすすめできます。
銀行で開業資金融資を受けるための方法
日本政策金融公庫に比べて、通常の銀行からの借り入れはハードルが高くなりますが、次のような方法を使えば、創業者の方であっても、比較的、融資がうけやすくなります。
同業者からの情報やネット等で開業資金融資に積極的な銀行を見つける
種別や評判などから積極的な銀行を見つける
金融機関の種類で選ぶ
銀行や信用金庫などは、それぞれが独自の方針による経営をしているため、金利や融資の姿勢が異なります。
金融機関にはその種類により、主に次のような特徴があります。
| 規模・支店数 | 創業融資への対応 | 融資額 | |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 大 | やや消極的 | 大 |
| 地方銀行 | 中 | 普通 | 中 |
| 信用金庫 | 小 | 消極的 | やや小 |
| 信用組合 | 小 | 消極的 | 小 |
以上のように、金融機関にはその種類によって創業融資への取り組みに多少のばらつきがありますが、はじめて金融機関を選ぶのであれば、信用金庫がおすすめです。
信用金庫は地域の中小企業を主なターゲットとした金融機関のため、創業融資への取り組みに積極的なところが多いだけでなく、融資の規模も数百万~1,000万円程度を得意としています。
なお、信用組合は信用金庫と同じく、地域の中小企業を対象とした金融機関ですが、信用金庫よりも規模や支店数が小さいところが多く、融資の規模もあまり大きくないため、信用金庫の次の候補として考えた方がよいでしょう。
周囲や同業者の評判から積極的な銀行等を見つける
以上のような特徴から、信用金庫は創業者の方が利用しやすい金融機関といえますが、信用金庫の中でも対応に差があるだけでなく、また、同じ信用金庫の支店の間でも違いがあります。
そのため、金融機関を選ぶときには、これらの基準を目安として、ネットの情報や実際に利用した同業者の評判なども参考にするのがおすすめです。
ただし、ネットの情報には、意図的によい、あるいは悪い評価がされていることもあるので、できるだけ出所の確かな複数の情報を参考にするようにしてください。
なお、融資に積極的な金融機関を見つけるうえで、最も確実なのが「自分で支店に出向いて相談する」ということです。
融資がスムーズにうけられるかは、銀行等の規模や融資姿勢だけでなく、担当者によっても大きく変わります。
もし、融資を成功させたいと考えている担当者であれば、「積極的にアドバイスしてもらえる」、「上役や信用保証協会へ交渉してくれる」などのサポートが期待できます。
しかし、あまり取り組みに積極的でない場合は、「役に立つアドバイスが少なく、事務的である」、「処理が遅い」などが考えられます。
そのため、実際に支店へ向いて相談することにより、その支店の雰囲気がわかるだけでなく、担当者の熱意を知ることができます。
開業資金に係る信用保証協会付き融資を利用する
創業者の方が銀行で融資を受けるときには、ほとんどの場合で信用保証協会の保証付融資を使うこととなります。
信用保証協会が保証をする方法には、次の2つのパターンがあります。
➀制度融資
制度融資とは、都道府県や市町村といった行政と金融機関、信用保証協会の3者が共同して、中小企業が融資を受けやすくするための仕組みをいいます。
制度融資におけるそれぞれの役割は、以下のとおりです。
| 対象機関 | 制度融資での役割 |
|---|---|
| 行政(都道府県等) | 制度融資の設計と運用 |
| 金融機関 | 自分の資金で融資をする |
| 信用保証協会 | 融資について公的な保証をする |
制度融資は、上記の3者が協調して融資をうけやすくするために行う、いわば「パッケージ型の融資」といえます。
制度融資ではあらかじめ融資をうけられる方や金利、上限額などの条件が決まっているため、中小企業や創業者でも容易に利用できるという特徴があります。
なお、通常の銀行よりかなり低めの金利※1で利用できますが、金利とは別途に信用保証料※2を負担する必要があります。
※1 東京都制度融資「創業」の場合 1.9~2.5% (2021.08時点)
※2 通常は1%前後。具体的な料率は申込人の属性にもとづき決定されます。
②信用保証協会の保証付融資
信用保証協会の保証付融資とは、信用保証協会が個別の融資について保証を行うものです。
制度融資がすべて一律の条件のもとで保証をするのに対して、この場合には個別に申込人の状況に応じて保証をするという違いがあります。
そのため、具体的な金利や返済期間などは、それぞれで異なったものとなります。
このように制度融資や信用保証協会の保証付融資では、利用のハードルが低く、創業者でも簡単に利用できるため、開業資金の調達方法としておすすめです。
自己資金を十分ためてから銀行に開業資金融資を申込む
創業融資を利用する場合には、自己資金が多いと、「それだけ計画的に資金を貯めてきたことが評価される」、「その分借り入れが少なくなり、健全な経営ができる」などのメリットがあります。
日本政策金融公庫の新創業融資制度や一部の制度融資では、融資の申込み条件として一定の自己資金があることが求められます。
たとえば、新創業融資制度の場合は「創業にかかる経費の1/10以上の自己資金」がないと申込みができません。
なお、自己資金として認められるものとしては、以下のようなものがあります。
・貯めてきた経緯が証明できる資金(通帳の記録など)
・法人の資本金や出資金
・事業のために融資申込み前に支払った経費(テナント保証金、内装費の手付金など)
・保有している有価証券
一方、次のようなものは自己資金として認められません。
・タンス預金(自宅で保管している現金など)
・他人からもらった資金(親兄弟からの協力金などは原則、OK)
・出どころを説明できない資金
以上のように、自己資金は融資申し込みの条件となっているだけでなく、金額が大きいほど審査に有利となります。
金融機関を問わず、開業資金に係る融資の審査が通りにくい理由
創業融資の審査は、事業計画書と自己資金の有無だけで行われるわけではありません。
それ以外にも押さえておくべきポイントがいくつかあり、その中には創業融資に特有のものもあります。
とくに、以下にあげる項目が遵守できていない場合は、融資失敗の原因となるため、事前に該当する項目がないかを確認してください。
創業者の過去の信用情報に難がある
申込人の信用情報に問題がある場合(破産歴や延滞等の記録)がある場合には、融資を受けることはできません。
個人情報の登録機関には「CIC」、「JICC」、「KSC」の3つがありますが、どの登録機関に事故情報が登録されている場合でも、融資は難しくなります。
また、法人で融資を申し込む場合には、代表者だけでなく役員についても事故情報がある場合には、融資が難しくなることがあります。
なお、事故情報は一定期間が経過すれば抹消されますが、その場合の開始は事故の原因が解消された日や免責を受けた日からとなります。
事故等があった日からではないことに注意してください。
CIC日本信用情報機構 http://www.cic.co.jp/
KSC 全国銀行個人信用情報センター https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
ICC日本情報信用機構 http://www.jicc.co.jp/
創業計画書に数字の裏付けが乏しく説得力に欠ける
事業計画書おいて納得のできる根拠が示されていない場合には、その計画は信ぴょう性の乏しいものとして評価されます。
とくに売上げについては、「なぜ、その金額が見込めるといえるのか?」をデータで示す他、契約書や見積もり慮などのエビデンスにより、明確にする必要があります。
創業者に開業予定業種の事業経験がまったくない
創業融資では、以前にこれから行う事業についての経験がどれだけあるかが重視されます。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、この目安の期間を6年としていますが、経歴の内容によっては3~4年程度の期間でも融資を受けることは十分に可能です。
ただし、経験がまったくない、もしくは極端に少ないといった場合には、審査での評価はかなり厳しいものとなります。
起業時、自己資金が極端に少ない、または全くない
日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する場合には、「創業に関する経費の1/10以上」の自己資金が必要となります。(一定の要件を満たす方を除く)
これは融資申込みの条件であるため、もし、この額に満たない自己資金しかない場合には、融資を受けることが難しくなります。そのため、そのような場合には、ムリに申し込むのではなく、自己資金の額にあわせた申込額に修正することをおすすめします。
家賃や光熱費、ローンなどの支払い遅れがある
融資を申込むときに、過去6ヶ月~1年の間に家賃、公共料金、各種ローン(住宅ローンを含む)、税金の支払いなどについて支払いの未納や遅れがある場合には、融資が難しくなります。
開業資金融資のおすすめ先
創業者については、信用力や経験が少ないため、銀行等から通常の融資を受けるのは困難ですが、次に紹介する融資制度は、いずれも政府が支援する制度のため、創業者であっても比較的、簡単な要件で利用することができます。
日本政策金融公庫の新創業融資制度
日本政策金融公庫の新創業融資制度は、創業者のみを対象とした融資制度で、次のような特徴があります。
対象者:新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間:各融資制度に定めるご返済期間以内
金 利:2.4~2.8% ※2021.08現在
その他の特徴
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること。
ただし、下記のいずれかに該当する場合には、自己資金要件を満たすものとされます。
<自己資金が不要とされるケース〉
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
1.➀現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
②現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方
4.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
5.技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
6.新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
7.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用を予定の方
なお、この制度は原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。また、法人については、代表者が連帯保証人とならないことができます。
信用保証協会の保証付融資
国の保証機関である信用保証協会では、制度融資と保証付融資という2種類の保証制度で、創業者や中小企業の融資を支援しています。
これらの制度を利用することにより、信用力の低い、または保証人を用意できない企業であっても公的な保証を受けられ、大手企業と同様の有利な条件で融資を利用することができます。
しかし、信用保証協会はあくまで信用の保証をする機関であり、融資そのものを行うものではないため、これらの制度を利用する場合は、金融機関や商工会経由で融資の申込みをする必要があります。
なお、信用保証協会を利用する融資の場合、信用保証協会から保証の承諾が得られない場合には、融資そのものが利用できなくなることにご注意ください。
戦略・開業資金は日本政策金融公庫で借りて、銀行融資は開業1年目以降に借りる
創業者の方が開業資金を借りる場合には、日本政策金融公庫の融資がおすすめです。
なぜなら、実績や経験がない状態でも融資をうけやすく、創業者に配慮した内容や条件となっているからです。
しかし、一度融資を受けた場合は、ある程度の返済実績ができるまで追加融資がされないため、短期間での再利用が難しくなります。
なので、開業後1年を経過し決算書の内容がある程度よい場合には、プロパー融資や制度融資にもチャレンジしてみましょう。
とくに、制度融資については、日本政策金融公庫と同じ程度の条件で申し込みができるため、借りやすいといえます。
また、通常の銀行との取引をしておけば、早くから実績を作ることができ、将来的に大きな額の融資の申込みができるようになります。
まとめ
創業者の方が開業資金の調達をするにはいくつかの方法がありますが、はじめに考えるべきなのが日本政策金融公庫の融資です。
その中でも新創業融資制度は、創業者専用の融資であり、比較的簡単な条件で最大3,000万円の借り入れをすることが可能です。
しかし、申込みにあたっては
・ 事業計画書の作成と提出が必要
・ 決算前の方については、創業にかかる経費の1/10以上の自己資金が必要となる
・ 信用情報に事故歴があったり、家賃などの支払い忘れがあると融資が難しくなる
などといった要件もあるため、申し込みの際にはこれらの見落としがないかに十分注意する必要があります。
また、制度融資などの信用保証協会の信用保証付融資も、公庫と同様の条件で借り入れができるため、あわせて検討することをおすすめします。