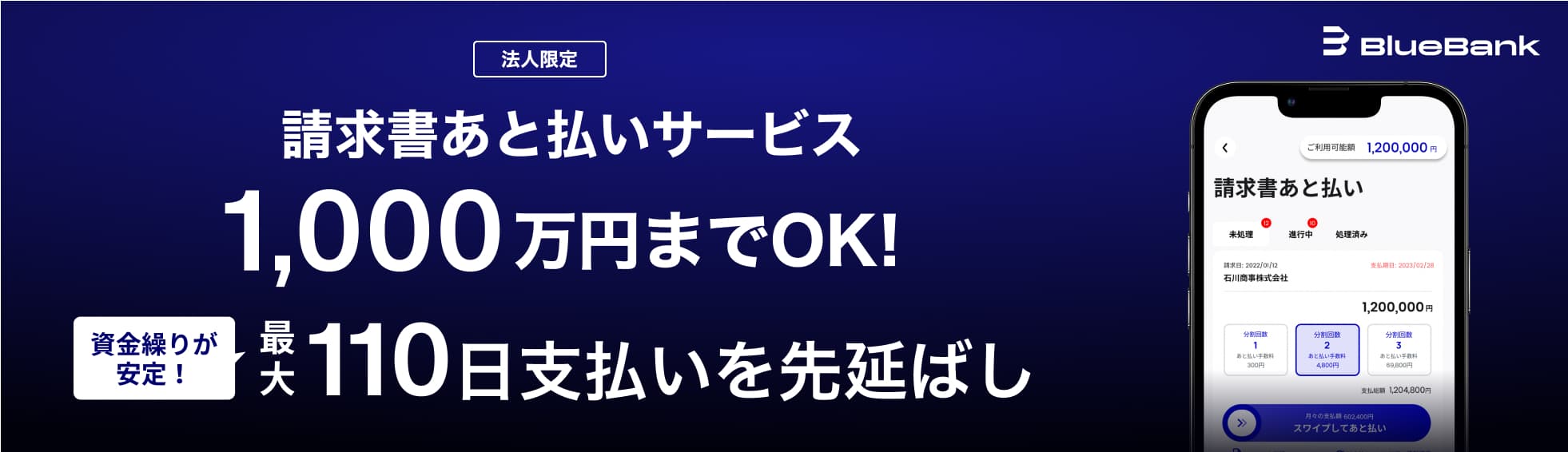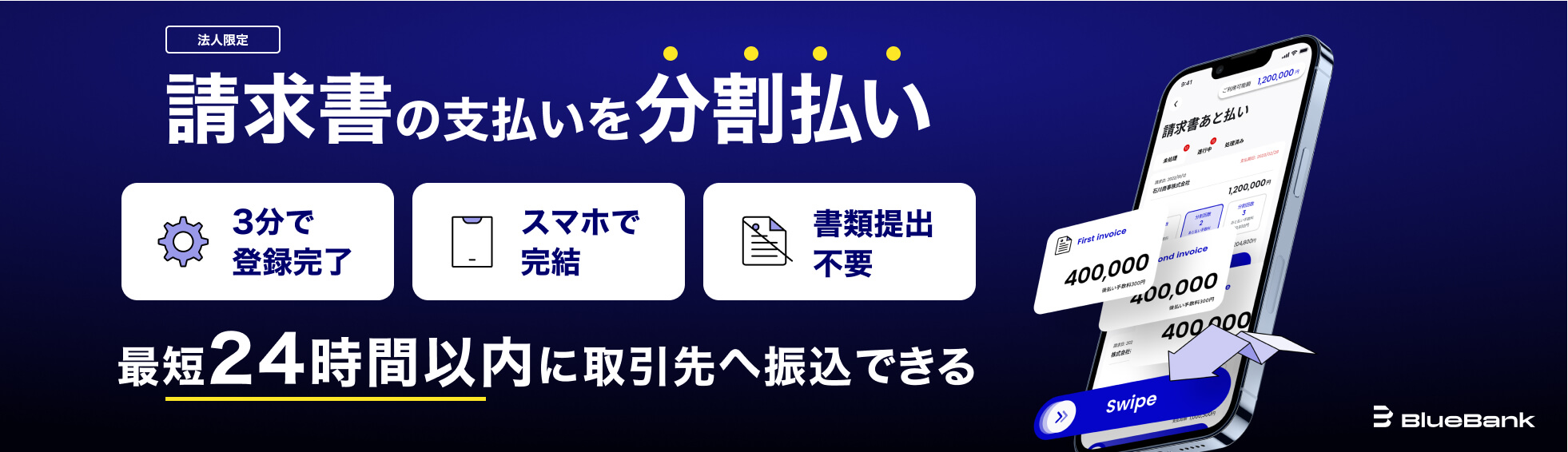開業準備の流れ・情報を集める
はじめて事業を行うのであれば、開業にどのような準備が必要なのかや、事業をどのように回していくのかといった知識が不可欠となります。ここでは、開業をする前に必要となる流れと準備について解説いたします。
情報を集めて開業のネタをみつける
2020年の中小企業白書によれば開業率は4.4%と最低水準であるのに対し、廃業率3.5%と高い水準で推移しており、とくに廃業率の高さには見過ごせないものがあります。
そのため、このような状況で開業するには、リスクの少ない事業のネタを見つけることが重要といえます。
事業のネタとしてはさまざまなものがありますが、開業をする際によくある失敗のケースが、「これまでになかったビジネスで開業する」というものです。これまでになかったビジネスであれば、ライバルが不在の上、シェアを独占でき、注目度も高いのでよいのではないかと、つい考えがちです。
しかし、これまでになかったものを社会に認知してもらうためには、よほどその内容が斬新か、もしくは有用性の高いものでなければなりません。また、このような製品やサービスを作り出すには、高い技術力やノウハウが必要となります。
さらに、仮にそのような製品やサービスを開発できたとしても、その時点では誰もその存在を知らないわけですから、その存在を認知してもらうには多額の宣伝広告費がかかります。
このようにこれまでになかった製品やサービスで起業をするのは、非常に難しいといえます。なので、早く、確実に成功させたいのであれば「すでにある製品やサービスに改良を加えたもの」で起業する方が、はるかにリスクが少なくて済みます。
たとえば、このような方法の一つとして、「自分の感覚や経験にもとづく起業」というものがあります。
これは、自分が解決したいことや、達成したいことのために商品やサービスを作ることを起点として、それを商品化するやり方です。
自分が不便に思っていることや、あったら便利と考えるものは、他の人もそう考えている確率が高いといえます。
もちろん、事前のマーケティングは必要ですが、これならばすでにある製品やサービスの延長線上であるため、周囲に受け入れられやすく、比較的販売も容易となります。
また、自分にビジネスのネタがないというのであれば、フランチャイズを利用するというのも一つの手です。
フランチャイズは、多少の研修や投資が必要となりますが、基本的に誰がしても成功しやすいノウハウがパッケージ化されているため、大きな失敗が少ないといえます。
以上のように、開業時にどのようなネタで勝負するかを考える上では、「自分がしたい」や「興味がある」ということは大前提とはなりますが、「そのネタはビジネスとして成功しやすいものなのか?」や「続けやすいものなのか?」という視点も忘れずに取り入れる必要があります。
ビジネスモデルを決める
ビジネスモデルについては、いろいろな表現がありますが、簡単にいえば「ビジネスをするために必要となる仕組み」のことです。
優れたビジネスモデルは、「誰に」・「何を」・「どのような方法で」・「いくらで」売るのかといったことが明確になっているだけでなく、これらの一連の流れが実現可能なものとなっていなければなりません。
一般的に、ある商品を販売する場合には
仕入れ(または製造) → 宣伝 → 販売 → 売上げというルートをたどりますが、それらの一つずつを確実に問題なく行えるものでなければ、ビジネスモデルとはいえません。
具体的には、各工程について、以下のような問題にしっかり答えられるものとなっているかがポイントといえます。
<仕入れ>
「どこからいくらで仕入れるのか?」
-具体的な店舗名や仕入れ価格の確認
「仕入れの約束はできているのか?」
-飛び込みでも販売してもらえるのか?代理店などを通す必要があるのか?
「安定して必要な量が仕入れられるのか?」
-品切れなどが起きないか?価格の変動は大きくないか?
「仕入れの条件はどうなっているのか?」
-現金か掛け仕入れか、ロット数や期間、掛けの場合の支払い期間など
<宣伝>
「どこに対して宣伝するのか?」
-ターゲットは誰か?そのターゲットは、どこに行けばつかまえられるのか?
「どのような方法で宣伝するのか?また、そのコストは?」
-チラシ撒き、ポスティング、口コミ、ネット広告、FAXDM、SNSなど
「どのくらいの効果が見込めるのか?」
-反応率や成約率はどの程度見込めるか?
「どのくらいの規模の宣伝をするのか?」
-めぼしい宣伝方法を複数使うのか?特定広告に絞って行うのか?
「どの程度の予算を使うのか?」
-初期投資はいくらにするのか?継続する場合の頻度と予算は?
<販売>
「どんな方法で販売するのか?」
-対面、ネット、その他の媒体、自販、委託など
「販売価格の決定」
-原価等の上乗せ方式、ライバルの価格を参考、自分の希望する額
「販売の条件はどうするのか?」
-現金か掛け売りか、ロット数や期間、掛けの場合の回収期間など
「どのようにセールスするのか?」
-セールスポイント、訴求の方法、接客方法、付加価値の創造など
ビジネスアイデアはどんなに優れたものであっても、実現できないものならば意味がありません。そのため、ビジネスモデルを作る際には、ビジネスのアイデアだけでなく、それを事業として成り立たせるため、工程の一つ一つについて実現できるレベルにまで落とし込むことが重要となります。
開業準備の流れ・事業計画を練る
ビジネスモデルが決まったら、次にそれを事業計画書としてまとめます。アイデアを具体的な事業計画書とすることで、それまでわからなかったプランの漏れや間違いに気づくことが可能となり、さらに内容をブラッシュアップすることができます。
事業計画書を作って具体的にアイデアを書面にする
事業計画書を作る上で重要なのが
・「事業として成立できる内容となっているのか?」
・「収支的に利益が出る内容となっているのか?」の2点です。
「事業として成立できる内容となっているのか?」については、ビジネスプランの箇所で説明した一つ一つの内容が実現できるかが課題となります。
まずは、事業計画書を作った際に、ビジネスの流れが問題なく実現できるのかを確認しましょう。そのうえで、もし、一か所だけでもあやふやな部分や、対応ができていない箇所がある場合にはその部分が現時点での課題となります。
自分で作った計画については、どうしても見方が甘くなりがちです。そのため、漏れや抜けがない計画を作るには、専門家などの意見を早めに取り入れることをおすすめします。そのうえで、足りない部分を徐々に埋めていくという作業をしていけば、実際に事業でも通用する事業計画書を作りやすくなります。
また、ビジネスとして考える場合には、仕組みだけでなく、利益の確保できる内容であるということも重要です。
どんなに仕組みがうまく回せるものであっても、十分な利益が出るものでなければ継続することはできません。
事業をする上で、主なコストとなるのは、「原価」と「販売管理費」です。
とくに販売管理費には、人件費や家賃、宣伝広告費などを含みますが、全体に占める割合が大きいため、少し見込みがあまいだけでもあっという間に利益がなくなってしまいます。
たとえば、創業者に人気の業種である飲食店の平均的な経常利益率は5~8%といわれています。つまり、1,000万円の売上げがあっても手元には50〜80万円の利益しか残らないということになります。なので、もし、売上げが500万円しかないのであれば、利益は25〜40万円となります。
しかし、この程度の利益であれば、余分な従業員がいる、客足が少し悪かったというだけで吹き飛んでしまいます。
もちろん、やり方次第でさらに多くの利益を残すことは可能ですが、そのためには工夫や努力が欠かせませんので、実現性の高い事業計画書を作るにはそれらも反映させたものとしなければなりません。
いずれにしても事業計画書を作るときには、あれもこれもと足していくのではなく、仕組みと利益が確保できる内容なのかという観点で作成する必要があります。
したいことが多いというのは悪いことではありませんが、あまり多くのことを事業計画書に入れてしまうと、どれも中途半端に終わってしまいがちです。
まずは、確実に最低水準を達成できる計画をつくり、それに足りない部分を埋めていくという方向でつくれば、計画がまとまりやすくなるだけでなく、実現のしやすい内容となります。
開業準備の流れ・開業資金を確保する
開業時にしなければならないこととしては、事業計画書の作成の他に資金調達の準備があります。資金に関するプランは事業計画書を作るうえでも必要ですが、これがどこまで現実的に仕上がっているかは、その後の事業の実施や融資にも大きく影響します。
開業資金がいくらかかるか出してみる
資金計画を立てるうえで、最初にすべきなのが「事業にどの程度の資金がかかるか?」を正確に把握することです。これがいい加減だったり、どんぶり勘定の場合には、「どの程度の資金を貯める必要があるのか?」や、「いくらの額の融資を申し込めばよいのか?」といった予測を立てることができません。
開業資金を考える場合、その内訳は「設備資金」と「運転資金」の2種類がベースとなります。
「設備資金」とは、店舗の建設費、内外装費、保証金、機器・什器類、車両といった、事業で使用する設備を購入するための資金を意味します。
一方、「運転資金」とは、家賃、人件費、光熱費、仕入れ代などの事業の運営をするうえで必要となる資金となります。
これらの開業資金は、原則として自己資金で賄うのが理想ですが、自己資金だけで不足する場合には銀行等からの借入れや出資などの方法も取り入れる必要があります。
開業にどの程度の資金が必要となるかについては、その事業の規模やかかる経費により大きく異なりますが、一般的には次のような資金が必要となります。
<運転資金>
・店舗の契約関連費用(仲介手数料、礼金等)
※店舗を借りて営業する場合
・家賃
・仕入れ代
・人件費
・水道光熱費
・宣伝広告費
・雑費
<設備資金>
・店舗の保証金
・内外装工事費
・厨房機器や備品の購入費
・看板代
・車両代
さらに、法人を設立する場合には、上記以外に以下の設立費用がかかります。
・設立登記の登録免許税
(株式会社の場合15万円〜、合同会社の場合6万円〜)
※資本金額×0.7%と比較した高い方の額。
・公証人の定款認証手数料
5万円(電子定款の場合は不要)
・収入印紙代
4万円(電子定款の場合は不要)
・雑費
2,000~3,000円(定款の謄本代等)
・専門家への報酬
5万円~
そのため、これから行う事業について「どの程度の資金が必要なのか?」と「自分で用意できる資金」並びに「借入れの出来る見込みの資金」を比較し、もし、資金的に厳しいような場合には計画の修正なども考える必要があります。
設備資金 + 運転資金 ≦ 自己資金 + 借入れ可能額
実現可能
設備資金 + 運転資金 > 自己資金 + 借入れ可能額
計画の縮小を検討
なお、一般的には、業種ごとで次の程度の金額が必要となるとされています。
飲食店 800〜1,500万円 美容室 600~1,500万円
ラーメン店 500~1,000万円 不動産業 300〜800万円
学習塾 200~1,000万円 士業 50~150万円
コンビニ 400〜3,000万円
※最低額は、所有店舗での開業の場合
HP作成やシステムの受託制作 100〜200万円 古物商 100~300万円
開業資金を貯める
開業にどの程度の資金が必要かの目途がついたら、次には、どの程度の自己資金を準備できるかを考えます。
自己資金とは、借入れや出資に頼らず、純粋に自分で用意することのできる資金です。
自己資金は、返済義務や利息を支払う必要がないだけでなく、出資を受けた時のような経営面での心配や配当も不要です。
なお、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する場合に「創業に関する経費の1/10以上の自己資金」が必要となりますが、親などからもらった資金はこれを自己資金とすることかできます。ただし、相手が親などであっても、借りたお金は自己資金と認められないため注意が必要です。
自己資金の例
・自分で貯めた預貯金
※ ただし、タンス預金は新創業融資制度の自己資金として認められない
・株式や国債などの有価証券
・親などから贈与された資金
・退職金や相続などで得た資金
・車などの現物の財産
自己資金以外の開業資金の調達方法を調べる
事業資金を準備するうえで最も望ましいのは「全額自己資金による調達」ですが、必要額が大きい場合には自己資金のみでの開業が難しいケースもあるため、そのような場合には、融資などの外部からの調達も検討する必要があります。
自己資金以外での資金調達の方法としては、次のようなものが考えられます。
① 日本政策金融公庫の融資の利用
創業者の資金調達に最も広く利用されているのが、日本政策金融公庫の融資です。
日本政策金融公庫は、中小企業や創業者に対して低金利、長期の有利な条件で貸付を行っています。
とくに日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用した場合には、最大3,000万円(運転資金については1,500万円)までの融資を無担保無保証で借り入れることができます。
そのため、 これから開業資金の調達をお考えの方には、最も実現可能性の高い資金調達方法といえます。
しかし、新創業融資制度を利用するためには
・ 創業にかかる経費の1/10以上の自己資金が必要
・ 開業後、2期(2年ではないことに注意)までしか利用できない
・ 創業計画書の作成が必要
・ 信用情報に問題がないこと
など条件を満たす必要があります。
② 制度融資の利用
多くの自治体(都道府県および市町村)では、金融機関や信用保証協会と協調して、それぞれがオリジナルの融資を行っています。このような融資を「制度融資」といいます。
具体的には、自治体が制度の設計や運用を行い、金融機関が融資をし、信用保証協会が保証の提供を行っています。ただし、制度融資の内容は自治体ごとですべて異なるため、具体的な条件や利用方法については、事業所が所在する自治体へ確認してください。
なお、制度融資は、同時に複数の申込みをすることはできません。たとえば、東京都新宿区の企業が、東京都と新宿区の制度融資を同時に申込むといったような使いかたはできないため、この場合はどちらか一つを選んで申し込むこととなります。
また、各制度融資では、すべての利用者について同じ条件が適用されるため、個別に融資条件の交渉をするとなどはできません。
③ ファンドなどからの出資を募る
ビジネスアイデアが画期的なものであったり、将来性の高いものであるような場合には、ファンドなどから出資を募ることも可能です。
ファンドからの出資は銀行融資などよりも大きな額の調達がしやすく、自己資金も必要とならないため、資金が少ない創業者であっても多額の資金調達ができるという特徴があります。
しかし、ファンドによる資金調達については、新規性の高い事業でないと採用されない、一定のリターンを求められることがある、経営権を支配される可能性があるなどといったデメリットがあることにも注意する必要があります。
④ クラウドファンディングで開業資金を募集する
最近では、クラウドファンディングにより、一般の方から資金を集めるという方法も広く行われています。クラウドファンディングによる資金調達の特徴は、ネットを通じて自社の商品やサービスを購入してもらうということにありますが、出資を募るという形式の支援なども広まりつつあります。
クラウドファンディングによる資金調達には、「実際にやってみないと、どのくらいの資金が集まるのかがわからない」、「継続して資金を調達することが難しい」といった課題もありますが、上手に利用すれば早期に顧客やファンを獲得できるため、集客方法としてもすぐれているといえます。
ただし、募集にあたっては、それなりの準備が必要となる、大きな金額を集めにくい、希望通りの額の調達ができるかどうかが不明などのデメリットもあります。
なお、自己資金をできるだけ多めに準備した方がよい理由としては、その後の借入れを少なくすることができるということの他に、もう一つ大きなものあります。
それは、「融資が使えない支払いに利用できる」ということです。
通常、融資が出るまでには申し込んでから約1~1.5ヶ月の時間がかかります。けれど、店舗の賃借や内装工事をする場合などには、その場である程度まとまった資金を払わなければならないことがあります。
例えば、テナントの契約関連の費用(手付金、保証金、当座の家賃など)や、工事の着手金はその場で支払わなければならないものです。しかし、この時点ではまだ融資は完了していないため、これらの資金は手持ちの資金から支払わなければならないこととなります。そのため、その時に十分な資金がないと正式な契約や工事への着手をすることはできませんし、これが原因で物件を変えざるを得なくなると、融資の手続きもやり直しとなってしまいます。
このように、自己資金がいくらあるかにより、必要な借入額が変わってくるだけでなく、事業の開始にも影響することとなります。
したがって、自己資金を準備するときには、全体的なバランスだけでなく、必要となるタイミングについても十分配慮する必要があります。
開業準備の流れ・退職手続きや保険への加入
事業プランの作成や資金計画ができたら、次にすべきなのが退職の手続きや保険への加入手続きです。とくに保険や年金の切り替えを忘れてしまうと、その後の保険の適用が受けられなくなったり、年金の受給額に影響することがあります。
勤務先に退職届を出す
現在、企業に勤務している場合には、最初にしなければならないのが、勤務先への退職の報告です。また、それと同時に各種保険などの切り替えも必要となります。いずれも一定の期限内にしなければならないものなので、スケジュールに沿って見落としがないように確認しましょう。
法律的には、退職の申し出期間は定められていませんが、一般的には就業規則などにより、「1か月前までに申し出ること」というような定めがある場合が多いようです。
しかし、これはあくまでも最低限の期間であって、実際には引継ぎや関係個所へのあいさつ回りなどが必要となるため、そのための時間も確保しておく必要があります。したがって、自分の状況をよく考え、周囲に迷惑とならないよう余裕をもって届出をするようにしましょう。
現在の会社の人間や取引先については、その後の取引先となってもらえる可能性が十分に見込めますが、非常識な退社は有力な見込み先を失ってしまうだけでなく、ケースによってはその後のトラブルの元となる可能性もあります。
社会保険への加入
法人として開業した場合には、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入は義務となっています。また、「すべての法人事務所(被保険者1人以上)」が対象となるため、たとえ社長1人だけの法人の場合でも社会保険に加入する必要があります。
個人事業主の場合は、原則として、健康保険については
・国民健康保険への加入
・業種ごとの健康保険組合への加入
・前会社の任意継続(2年間)
のいずれかを選択することとなります。
なお、国民健康保険については扶養という制度がないため、家族がいる場合にはその人数分の保険料を支払わなければなりません。
また、年金については国民年金の第1号被保険者となります。
ただし、個人事業の場合であっても、常時従業員を5人以上雇用し、以下の16業種に該当する場合には、社会保険への加入が義務となります。
※製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒体斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業
個人事業・法人を問わず、加入義務があるにもかかわらず、社会保険への加入をしない場合には、年金事務所から加入への指導が行われますが、引き続き未加入の場合には、立入調査の実施や、職権による加入手続等の措置が取られる他、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
労働保険への加入
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
法人については、労働者を一人でも雇用している場合には、労災保険と雇用保険のいずれについても加入が義務となります。
個人事業主については、本人やその家族、役員を含め雇用保険に加入することができません。
ただし、原則として従業員を1人でも雇っている場合には、以下の条件に該当する人を雇っている場合を除き、雇用保険に加入することが義務となります。
・週の所定労働時間が20時間未満の従業員
・31日以上の雇用見込みがない従業員
・一定の要件を満たす日雇い労働者と季節労働者
また、労災保険についても、本人は加入することができません。
ただし、雇用保険と同様、従業員を1人でも雇っている場合には、加入が義務となりますが、この場合には雇用保険の場合のような例外規定はありません。
なお、労働保険についても加入義務があるにもかかわらず、労働保険への加入をしない場合には、年金事務所から加入への指導、追徴課税の他、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
開業準備の流れ・開業を届ける
開業時には、開業届の他、業種に応じて許認可を取得する必要があります。
開業届の提出
・「開業届」(税務署)
個人が事業主として活動を始めるときは、開業後1ヶ月以内に税務署へ「開業届」を提出する必要があります。開業届を提出しなかった場合でも罰則や過料などはありませんが、銀行口座の開設や融資申込ができなくなってしまうことがあります。
・「法人設立届出書」(税務署・都道府県・市町村)
法人で開業した場合には、「法人設立届出書」を会社設立の日から2か月以内税務署へ提出します。また、法人については、これとは別に都道府県や市区町村に対しても、同じく「法人設立届書」を提出する必要がありますが、こちらの提出期限は、都道府県等により異なります。(目安としては法人設立後15日〜1ヶ月)
その他の届出や許認可
・「青色申告の承認申請書」(税務署)
確定申告を青色申告で行う場合には「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。提出は義務ではありませんが、これを期限内に出さないと青色申告の特別控除や損失の繰り越しといった、税務上の特典を受けることができなくなります。
この申告書は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後の場合には、事業開始等の日から2月以内)に提出する必要があります。
・食品衛生責任者(飲食店)
飲食店の営業する場合には、食品衛生責任者またはこれに代わる資格(栄養士・調理師等)を取得して、施設ごとに1人以上を配置する必要があります。
・営業許可(飲食店)
飲食店の営業をする場合には、食品衛生責任者の配置だけでなく、保健所の営業許可を取得する必要があります。なお、営業許可の申請にあたっては、申請書を提出するだけでなく、その施設が一定の基準を満たしているかどうかを検査する店舗の実地検査にも合格する必要があります。
・深夜における酒類提供飲食店営業の届出(飲食店)
飲食店で、「深夜営業」(午前0時から午前6時までの間に、酒類を提供する営業)をする場合には、所轄の警察へ「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を提出しなければなりません。この届出が提出されるまでは、通常の営業をすることはできますが、深夜営業をすることはできません。
開業の失敗を避け、成功に導くにはどうしたら良い?
新規開業で、できるだけ失敗を少なくするためには、次のような点に注意するとともに、必要な準備をしておくことをおすすめします。
① 開業を見越した経験を積んでおく
開業をする際にはこれから行おうとする事業についての経験が重要となりますが、単に表面的な経験を積めばよいというわけではありません。
経営をする上では基本的な業務やオペレーションについての知識があることは当然ですが、 実際の経営においては経験者ならではの能力も必要となります。
例えば「取引先との交渉」、「経理事務や現金の管理」、「従業員やパートの募集・採用」、「商品やサービスの開発」、「資金繰り」、「金融機関からの融資の調達」などといった行為は、従業員の立場では行うことができないものです。
しかし経営を始める場合には、単なる製造や販売調理などといった作業とは別に、これらのことも同時に行わなくてはならなくなります。
そのため、開業をするための事業経験を積む場合には、単なる事務やオペレーションだけを学ぶのではなく、上記のような経営に関わる業務についてもあらかじめ習得しておく必要があります。
② できるだけで小さな規模で始める
開業をする時にはあれもこれもと欲張り、大きな資金を投入して事業を始める方が少なくありませんが、できればはじめのうちは小さな事業で始めることをおすすめします。
大きな規模となるほど、資金繰りや従業員の採用、必要な売上額の確保などが困難となるため、店舗の運営が難しくなります。また、開業に多額の資金がかかる場合には、必然的に借入額も多くなるため、その後の資金繰りの悪化の一因となります。
しかし、設備や従業員数をできるだけ抑えた小さな規模での開業であれば、大きな売上げを上げるのは難しくても、運営のオペレーションや従業員の管理などが容易となるため、その分経営がしやすくなります。
また、それとともに必要な資金額も少額で済み、多額の借り入れをする必要がなくなることから、 少ない負担で事業を始めることができます。
③ できるだけ自己資金を多くする
開業にあたってはできるだけ自己資金を多く準備するようにしましょう。
開業資金に対して自己資金が少ない場合には、必要以上に多額の借り入れをしなければならなくなります。
また、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する場合には、「創業経費の1/10以上の自己資金」が必要となりますが、これはあくまでも申し込み時の最低要件であって、実際に借り入れのできる金額の目安は「自己資金の3〜4倍程度」というのが一般的です。
つまり、自己資金が少ない場合には、最低要件を満たせない可能性が生じるだけでなく、実際に融資を受ける場合にも、その額は自己資金の額に応じた小さな額となってしまいます。
さらに、テナントを借りる場合の契約費用や内装工事が必要な場合の着手金などについては、手持ちの自己資金からこれらを支払わなくてはなりません。
そのため、どのようなタイミングでいくらの資金が必要となるかを事前によく考えた上で、それに見合った自己資金を用意する必要があります。
④ 実際の経営を意識した事業計画書を作成する
事業計画書は、主に
・自分の事業プランの内容を確認するため
・金融機関から融資を受けるため
という2つの目的のために作成します。
ただし、いずれの事業計画書も、単に表面的な内容やプランを記載したものではなく、実際の経営に役立つものでなければ意味がありません。
そのためには、その内容がすぐにでも事業が始められるだけの具体的かつ実現可能性の高いものとなっている必要があります。
もし、事業計画書の段階で、プランが決まらない、内容に無理があるといった場合には、実現できない計画となってしまうため、作業レベルにまで落とし込んだ詳細なものを作るようにしましょう。
また、事業計画書を作る上で、どの程度の収支が確保できるのかは重要なポイントの一つとなりますが、とくに金融機関へ提出するものについては、必ず金融機関への返済が可能となるだけの利益が確保できる内容となっている必要があります。
⑤ 他の成功例や失敗例を分析する
他の事業者の成功例や失敗例は、これから自分で事業をする上での貴重な資料となります。
とくに同じ業種に関する事例は参考になる部分が多いため、書籍やネットからだけでなく、できるだけリアルな情報も集めるようにしましょう。
なお、これらの事例を参考にするときには漫然と見るのではなく、「この会社は自分と同じシステムを採用しているのになぜ、失敗したのだろう?」とか、「この会社の成功事例は自分でもマネできないだろうか?」のように、自分の事業に置き換えた視点で参考にすると、具体的な経営に活かすことができます。
まとめ
開業をするときには、短期間で数多くの準備をしなければなりません。もし、準備がいい加減だったり、おろそかな場合には、開業までの時間が長くなるだけでなく、その後に失敗するリスクも高くなります。
そのため、できるだけ失敗のリスクを少なくするには、しなければならない準備の内容を確認するだけでなく、あらかじめ予想される手続きやリスクへの対応を考えるとともに、他の成功例や失敗例なども参考にする必要かあります。
また、もし、プランの内容や進め方に不安がある場合には、早い段階で専門家に意見を聞くということなどもおすすめできます。