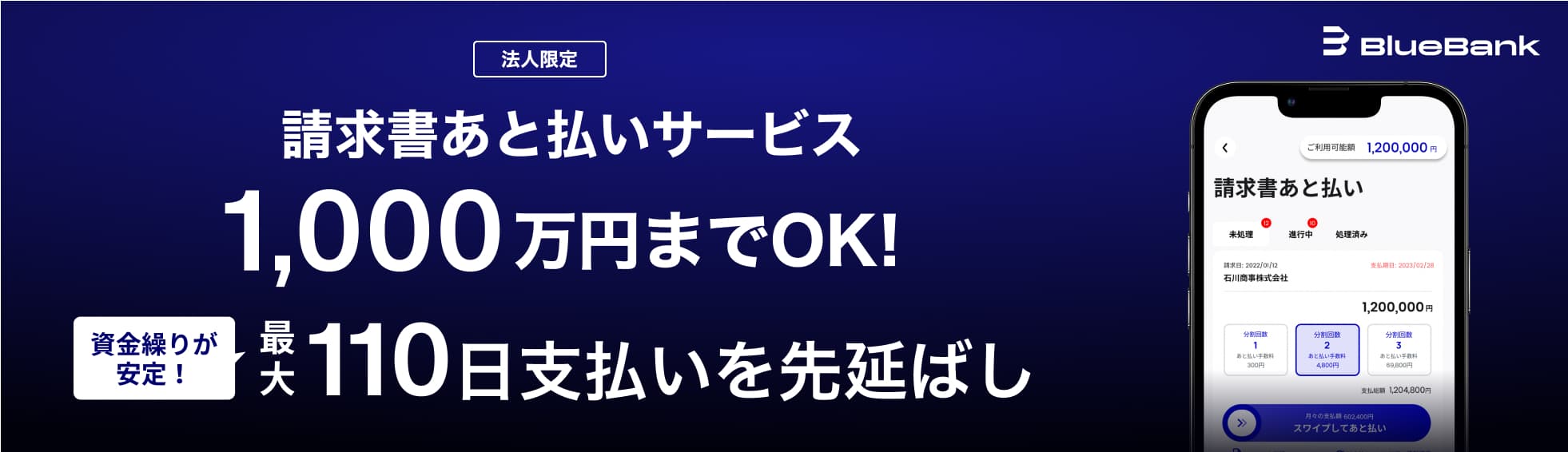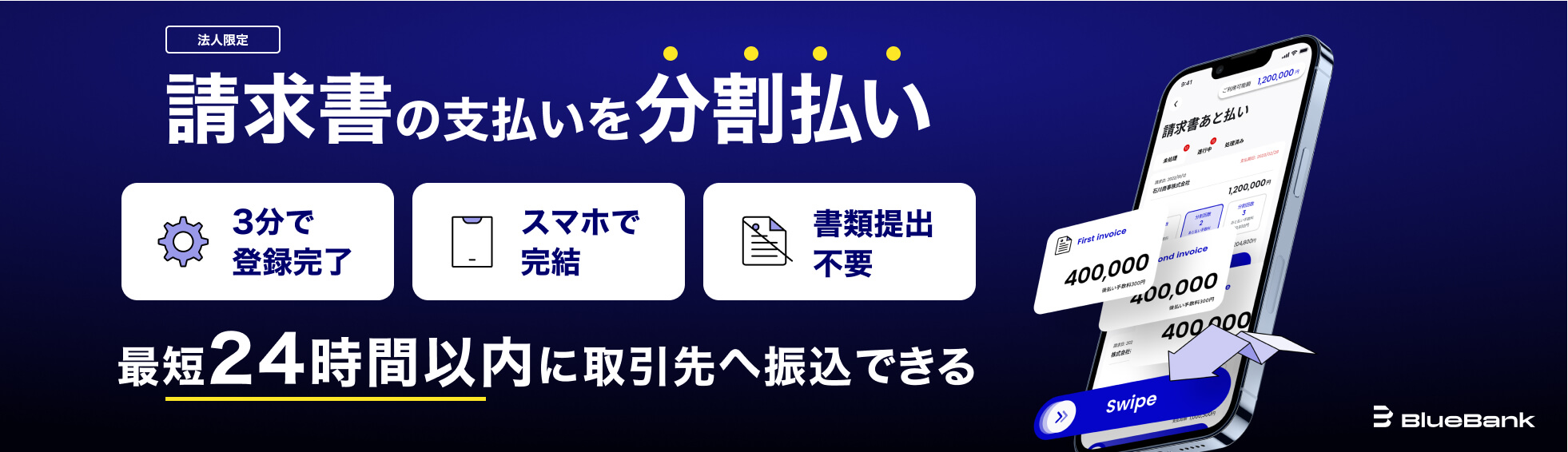事業計画書にまつわる本はとても多く出版されています。
ネットでも基本的な情報収集はできますが、きちんと理解しようと思えばいくつか本を読んでみるのがおすすめです。
事業計画書の世界はとても奥深く、ビジネスをやっていれば常に事業計画という言葉がついて回ります。
昔も今も、事業計画書は起業家やビジネスマンにとって関心事であることは間違いありません。
ですが、核心に迫る内容をネット上で見つけるのは至難の業。信頼できる著書を選び、起業準備に役立てましょう。
>>創業時の融資審査が通る?事業計画書を上手に書くための3つの方法 【事業計画書の上手な書き方】
事業計画書に関するオススメ本 9選
試しに、Amazonでジャンルを本に限定し「事業計画書」で検索すると、400件以上もの本がヒットします。
いったいどの本から読めばいいか途方に暮れてしまいますが、ここでは「これから開業したい・会社設立したい」と思っている人にとっておすすめの本を7つ、厳選してご紹介します。
ぜひ参考にして下さい。
②自分でパパッとできる事業計画書
③事業計画書は1枚にまとめなさい―公庫の元融資課長が教える開業資金らくらく攻略法
④A3一枚でつくる 事業計画の教科書
⑤金融機関からお金を引っ張る事業計画書のつくり方
⑥起業のファイナンス
⑦真剣教室 資金調達の教科書
⑧プロ直伝! 成功する事業計画書のつくり方 (マンガでわかる! ビジネスの教科書シリーズ) (ナツメ社)
⑨カラー版 マンガでわかる 事業計画書のつくり方(西東社)
①マンガでやさしくわかる事業計画書 著:井口嘉則
ビジネス書ジャンルで過去に大ヒットしたこの本。 書店で見かけたことがあるという方も多いのではないでしょうか。人気のため、Kindle版でも販売されています。
本書はストーリー仕立てになっており、ビジネスなどやったことのない28歳の女性が新規事業で家業の造り酒屋を再建させるというストーリーです。
起業というと意識の高い人がやるものというような先入観はありませんか?
そうした気後れを感じている方も、本書を読めば前向きな気持ちで起業準備に取り組めるはずです。
漫画で大まかな内容を解説した後は、柔らかめの文章で詳しく説明してくれます。
感情移入しながら事業計画の大切さについて学ぶことができるので、まずは入門編の本を読みたい、あまり難しい本は避けたいという方にオススメです。隙間時間にでも無理なく読み進めることができます。
入門編といえど事業計画書を作成するのに絶対に必要な基礎は一通りおさえてあるので、入門書として安心して薦めることができる一冊です。
本書の著者の井口氏は、起業を志している学生など若者でも抵抗なく読める本を作ろうと思い本書に取り掛かったということです。
そんな著者のあたたかい想いが随所に溢れる、元気の出る内容になっています。
②自分でパパッとできる事業計画書 著:石井真人
まずはやってみて覚えるタイプの方にはこの本をおすすめします。
最低限の説明はしっかりとされており、見ながら手を動かして事業計画書がとりあえず作れてしまいます。
構えずに取り組めるのが本書の良いところです。
特に本書には、実際に使われる事業計画書が7業種分サンプルでつけられています。
テンプレートもダウンロードできるので、初めて事業計画書を作る方にはおすすめです。
本書では、事業の段階をレベル1~3の3つに分けて解説しています。 このレベルが上がるにつれて、事業計画書に求められる精緻さも上がっていくということです。
本書の表紙にはA4用紙1枚で簡単に作成ができるとありますが、これはレベル1、ビジネスや企画の全体像を固める企画段階のことを言っています。
これがレベル2になると、売れる根拠をしっかり示すことができ、事業の基盤を確実なものにしていく段階になります。
この段階だと企画書はA4用紙10枚になります。
レベル3になると、先ほど述べた売れる根拠に加え、儲かる根拠・実行できる根拠まで必要になります。
事業規模を拡大していくのがこの段階になります。事業の成長に合わせて、必要な事業計画書の形も変わっていくのです。
皆さんはこれから起業を志しているところなので、レベル1か2の段階ではないでしょうか。
何事もイメージを固めるところから始まりますので、まずはA4用紙1枚の企画書から手を動かして作ってみましょう。
実際に作ってみると、理解が深まり実務にも大いに役に立つことと思います。
③事業計画書は1枚にまとめなさい―公庫の元融資課長が教える開業資金らくらく攻略法 著:上野光夫

事業計画書は1枚にまとめなさい―――公庫の元融資課長が教える開業資金らくらく攻略法
日本政策金融公庫は小規模事業者の強い味方です。 信用力のない創業希望者に融資をしてくれるのが公庫なのです。
本書は、公庫の元融資課長が書いた本ということで実務的な知識もさることながら、公庫の融資担当者の気持ちがあちこちににじみ出ているのがポイントです。
どうすれば金融機関はお金を貸したくなるのか。それが余すことなく記されているのがこの本です。
金融機関の融資担当者は、経営者の人となりだけではなく、経営に必要となるリソースなどのシビアな部分もしっかりと見ています。
いかに創業者が人間として魅力的でも、貸したお金が返ってきそうにないと思われてしまっては絶対に融資を受けることはできません。
しかし、このシビアな部分も書類の書き方次第で大きく印象が変わってきます。
その表現方法を教えてくれるのが本書なのです。
金融機関の担当者も、実際はこうだろうと思っていても経営者が言っていない・書いていないことを融資の稟議書類に書くことはできません。
資金調達がスムーズにいく会社というのは、金融機関向けの書類の書き方を分かっている担当者が中にいるものです。
金融機関の内情をここまで書いて大丈夫なのだろうか、とハラハラしてしまうほど正直に書かれた一冊です。
資金調達の手段として融資を第一に考えている方なら読んでみてまず損はありません。
④A3一枚でつくる 事業計画の教科書 著:三浦太
ビジネスを取り巻く世相はめまぐるしく変化しています。 先進国の経済成長は鈍化し、多くのスモールビジネスが独自の視点で新たな市場を開拓するようになってきました。
スモールビジネスが多くなると、事業者単体でリスクを負うことが難しくなります。
そのため、他社との事業提携の機会も増えてきました。
例えば大企業のオープンイノベーションやM&A、ビジネスマッチングや業務のアウトソース(BPO)はもはや珍しいことではありません。
創業間もない小さな企業でも、その実力や着眼点次第では大企業とコラボレーションしたり、一気に潮流に乗ることが普通に起きるようになっていきているのです。
こうした世相を反映し、経営者が事業内容について説明する機会は非常に多くなりました。
機会が多くなると1件あたりの検討にかけられる時間は必然的に短くなるので、「簡潔に・わかりやすく」事業を説明する能力が近年の経営者には必要とされています。
他人に自分の事業を魅力的にかつ分かりやすく伝えるには、経営者自身の脳内が整理されていないと魅力的なプレゼンはできません。
事業計画書にしても同様で、旧来型の分厚く読むのに時間のかかる事業計画書は嫌われ、簡潔で要点を押さえた事業計画書が好まれるようになってきているということです。
著者の三浦氏はこれに着目し、事業計画は「A31枚でまとめられるくらいにブラッシュアップすべきである」と主張しています。
監査法人、会計士として多くの企業を見てきた著者の目は確かで、A3用紙1枚しかないフォーマットにも関わらず、必要な内容が網羅された「洗練された」事業計画書が作れるようになっています。
自分の頭を整理して、いつでも誰にでも簡潔に説明できるようになりたい。協力者を多く持ちたい。
そんな起業志望者におすすめの1冊です。
⑤金融機関からお金を引っ張る事業計画書のつくり方 著:田中秀一
さて、先ほど金融機関出身者の著書を紹介しましたが、金融機関も考え方は多種多様。
金融機関に精通した、違う人物の書いた本を読んでおくのも様々な金融機関と付き合う上で参考になるでしょう。
本書の著者は金融機関出身ではないものの、中小企業診断士という難関資格を保持する民間出身者。
日本マクドナルドや富士電機ITソリューションを経て、経営コンサルタントとして独立しています。
本書で面白いのは、具体的な事例を提示して論理を展開していること。 例えば、次のような章が含まれています。
磯野家のマスオさんが早期退職で起業するとしたら…
実際に早期退職して起業しようと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうしたユーモアを交えて書かれた本なので、勉強しながらも楽しく読み進めることができます。
資金繰り表など欠かせない書類の作成方法も押さえつつ、「経営者の魅力をいかに書類に表現するか」という、人物を前面にアピールした事業計画書づくりを学ぶことができます。
もちろん融資につなげる書き方を意識しているので、金融機関の融資担当者にも人情派はまだ残っているものということの表れでもあります。
⑥起業のファイナンス 著:磯崎哲也
もし、融資でなく出資やベンチャーキャピタルからの資金調達を検討しているのであれば、本書は必ず読んでください。
資金調達は融資しか検討していないという方は本書を読む必要はありません。
エクイティファイナンスの入門書としてこれほど分かりやすい書籍は見たことがありません。
ベンチャー企業の財務担当は必ずと言っていいほど本書でエクイティファイナンスの勉強をしています。
エクイティファイナンスとは、ざっくり言うと株式と引き換えに出資してもらい資金調達をすることです。その仕組みから丁寧に解説してくれています。
融資は資金調達の手段のひとつにすぎません。
本書を読むと、他の資金調達方法と比べて融資を受けることのメリット・デメリットも知ることができます。
投資家は金融機関とは全く違ったものの考え方をしています。
金融機関は大きなリターンがなくても、確実に貸したお金が返ってくることを重視します。
それに反して投資家は、出資金は返ってこないこともよくある話ですので、企業が上場したりして株価が上昇し、その際に株式を売却して大きな利益を得ることを目的としています。
事業計画書を見せる相手が誰かで強調すべきポイントは変わります。
投資家の考え方を知るという点でぜひ本書には目を通しておいていただきたいと思います。
⑦真剣教室 資金調達の教科書 著:加藤雅士
資金調達の手段の一つに「補助金」というものがあります。
日本経済の落ち込みが続き、起業志望者もずいぶんと減ってしまいました。
企業の新陳代謝は経済の活力そのものです。政府もそういった背景もあり様々な起業を後押しする補助金を運用しています。
国のもの、都道府県のもの、自治体のもの、主体は様々ですが、補助金の落とし穴は「当然の権利」ではないということです。
知っている人だけが使えるものなので、知らなくて申請をしなかったから後追いで申請できるという性質のものではありません。
知らないとまるごと損してしまいます。
しかし、世の中にある補助金は本当に多く、要件も複雑。 それをまとめて解説してくれているのが本書です。
安倍元首相が打ち出した「アベノミクス」では、中小企業支援になんと2兆円もの予算が割かれていました。
起業を志す者にとっては、またとない恩恵を受けられる大きなチャンスです。
例えば、以下のようなものがあります。
・ものづくり補助金(採択されれば最大1,000万円)
・新事業活動促進法に基づく特別融資枠の活用(最大8,000万円)
事業計画書づくりに夢中になっていると、補助金や有利な制度のことをうっかり忘れてしまいます。
なぜなら、質の良い事業計画を立てることができれば無理なく融資や出資を受けられてしまうからです。
しかし、当然のことながら返済不要な資金が多いに越したことはありません。 経営の自由度がずっと違ってきます。
申請の抜け漏れをなくすために、補助金についての本に一度は目を通しておきましょう。
本書のポイントは、実際に補助金の採択に成功した事業計画書のサンプルが本書の中で公開されていることです。
大いに参考になることは間違いありません。補助金が取れる事業計画が作りたいという方にはオススメの一冊です。
⑧プロ直伝! 成功する事業計画書のつくり方 (マンガでわかる! ビジネスの教科書シリーズ) (ナツメ社)

プロ直伝! 成功する事業計画書のつくり方 (マンガでわかる! ビジネスの教科書シリーズ)
マンガの主人公が、事業計画の知識のない所から、事業計画書を作成するストーリーです。 ストーリーを追いながら、事業計画書作成手順を学んでいきます。
魅力のある事業のアイデアの見つけ方、ビジネスモデルの考え方、利益をどうやって出していくかなど、事業成功に向けて事業計画を立てていきます。
起業や新規事業の立ち上げにおいても役に立つでしょう。
難しいと考えがちな事業計画書がマンガ形式になっていますので、読みやすく理解しやすいです。
⑨カラー版 マンガでわかる 事業計画書のつくり方(西東社)
カラーで見やすいマンガで事業計画の基本から事業計画書の立て方までが説明されています。 起業、新規事業を立ち上げ成功に向けての事業計画書の作り方を学んでいくことができます。
マンガだけでなく、図表や解説までカラーでとても読みやすくなっています。購入特典として、9つの書式がダウンロードできます。
内容は、アイデアやビジネスモデル、収益計画、行動計画、事業計画サンプルなどと豊富にありますので、計画段階でいろいろ役立ちます。
失敗しがちなポイントについてもケーススタディ形式で説明がありますので、こういったポイントも読んでおくといいでしょう。
成果を生む事業計画のつくり方(日経文庫)も手軽に持ち歩ける文庫版サイズの書籍もありますので、手軽に事業計画について読むこともできます。
このような書籍も参考にしながら、起業から事業計画など事業の立ち上げについての知識も得て、具体的に検討し進めていくといいです。
事業計画書 参考したい本ガイドのまとめ
読んでみたい本は見つかりましたか? 紹介した本はどれもAmazonなどのネット書店で購入できるものばかりです。
かつ、柔らかい内容のものから名著と呼ばれる類のものまで幅広くご紹介しました。
良い本は、経営のあらゆるタイミングで必ず参考になります。 もちろん起業準備のために読む本として紹介はしていますが、事業が軌道に乗ってしばらくたってから読み返すと、また違った発見があるものなのです。
あなたの会社経営の右腕となるバイブルと出会えることを願っています。