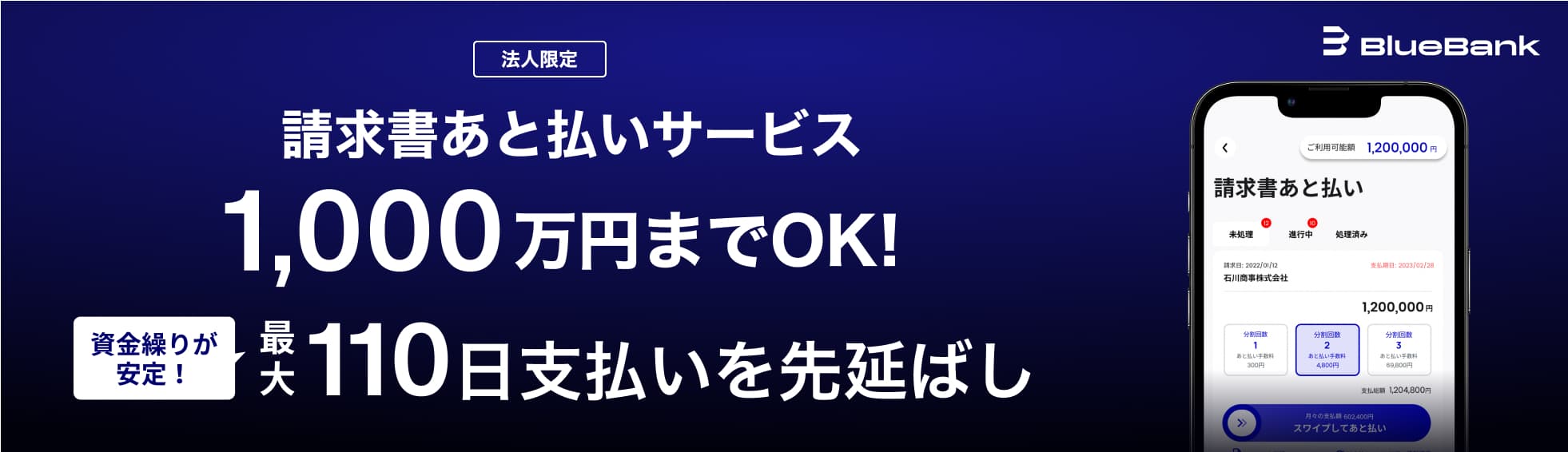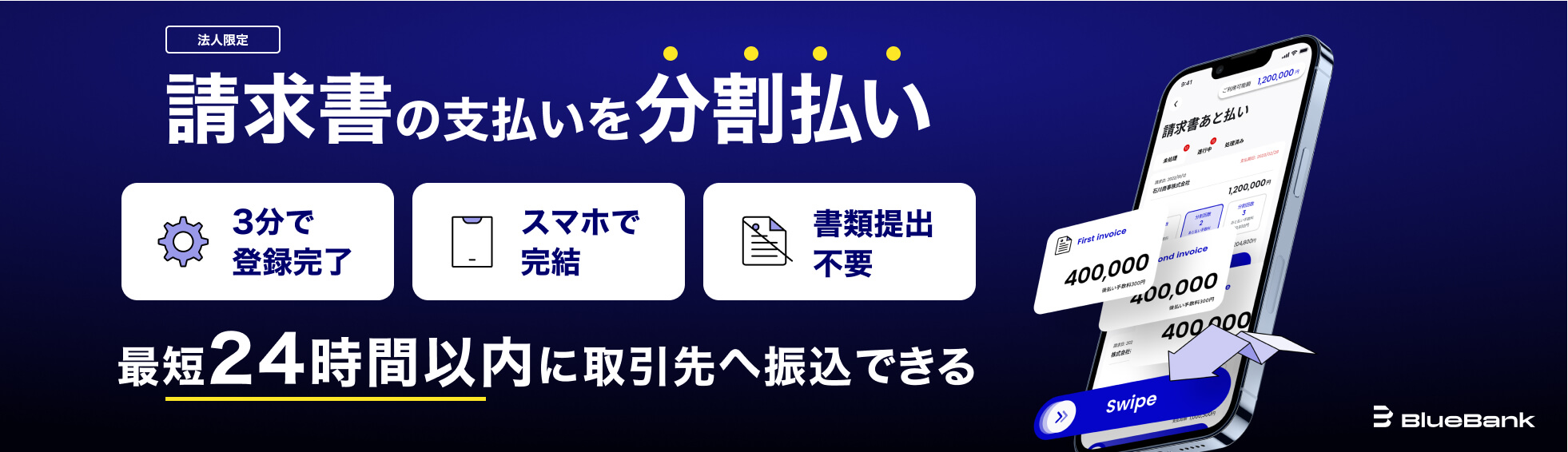融資を必要とする際には、金融機関の融資担当者にまず事業計画書を提出することになります。
そこで事業計画への評価がなされるわけですが、その際のカギとなるのが「財務計画書」です。
融資を受けられる事業計画書かどうかは財務計画書で決まる、と言っても過言ではありません。
そんな融資に強い財務計画書の作り方について、この記事で順に確認していきましょう。
財務計画書とは何か

そもそも財務計画書とは何なのかをまず正確に把握しましょう。
主に3つの財務諸表によって構成されます。
・貸借対照表
・資金繰り表
これらに表される数字こそ、企業財務の主な構成要素ということになります。
それぞれが何を表したものなのかを適正に把握し、順に作成していくことで企業財務を押さえた事業計画書を作成していきましょう。
財務計画は根拠のある数字で作成する
財務計画を作成する際に気を付けたいことがあります。
それは根拠のある数字で作成をするということです。
よくやりがちな財務計画の作り方が、単なる目標だけの数字で構成してしまうやり方です。その根拠となる数字を必ず用意しましょう。
既に稼働していて実績のある会社であれば、自社の前期・前々期の財務諸表は必ず参照にします。
現実の数値とその実績を生んだ自社の事業活動や市場の動向を分析し、それを踏まえて未来の数値やその根拠となる事業活動について計画に盛り込んでいきます。
信憑性のある財務計画は必ずこのような形で成り立っています。
【財務計画】損益計算書の作成方法

具体的な計画の作成方法を見ていきましょう。まずは損益計算書です。
損益計算書は、「Profit&Loss Statement」でPLとも呼ばれ、一定期間における事業の売上や経費などの収支を示した表のことです。
損益計算書の大事なポイントは、最終的な「当期純利益」がプラスで終えられていることです。
自社の前期、前々期の損益計算書はどうなっているでしょうか。
「売上高」から「売上原価」「販売費及び一般管理費」「営業外収益・営業外費用」「特別利益・特別損失」「法人税等」を差し引いて、最後に残ったのが「当期純利益」です。
これを踏まえて順に見込みを立て、損益計算の計画を月毎に立てましょう。
・売上見込みを立てる
商品・サービス毎に売り上げ見込みを分けて作成します。根拠となる市場動向のデータを添えると説得力が増すでしょう。
・売上原価見込みを立てる
売上に連動して、売上原価の見込みを立てます。
商品をまとめて仕入れて値引きを図る、などのコストカット策も同時に検討します。
・販売管理費及び一般管理費の見込みを立てる
基本的には「固定費」にあたる部分ですので、売上の大小に関係なく発生します。
どれだけの売上を最低限確保する必要があるのか、を示す損益分岐点売上高に大きく影響する部分です。
・営業外収益・営業外費用の見込みを立てる
本業以外で上げることのできる収益を計画します。資産運用などで収益を生めないかをこの段階で考えることになります。
・税額を算出する
特別収益・特別損失はイレギュラーな案件に対して発生するので、計画には入れません。
最後に「法人税」「地方法人税」「法人住民税」「事業税」などの税金を組み込んで、最終的な当期純利益を算出して、損益計算書の計画を完成させます。
【財務計画】貸借対照表の作成方法

続いて、貸借対照表の作り方を見てみましょう。
貸借対照表は、「Balance Sheet」でBSとも呼ばれ、ある一定の時点において企業がどれぐらいの資産や負債や権利などを所有しているかを示した表です。
損益計算書作成時のように毎月分で作成することもできますが、まず大事なのは決算期末時点の貸借対照表を作成することです。
前期決算書の貸借対照表をスタート地点とし、作成した一年分の損益計算書の計画を入れ込むと当期末にはどんな状態になるかを算出しましょう。
貸借対照表は「流動資産」「固定資産」「流動負債」「固定負債」「純資産」の5要素によって成り立っており、この5要素がどのようなバランスで成り立っているかを融資担当者はチェックします。
押さえておきたい経営指標
融資担当者はあらゆる経営指標をもって、このバランスをチェックします。
その中で必ず押さえておきたいのが「総資本経常利益率」です。「Return On Assets」でROAとも呼ばれます。
総資本がどれだけの利益を生み出しているか、を示した指標で
の式で算出されます。
業種により異なりますが、一般的には10%程度を確保できると安心です。
業種別の総資本経常利益率の平均を中小企業庁のホームページで確認することができますので、自社事業が属する業種の平均を確認して上回れているかどうかを把握すると良いでしょう。
【財務計画】資金繰り表の作成方法

最後に、資金繰り表の作り方です。
資金繰り表は、一定期間における企業の現金の出入りを示した表のことです。
収支で赤字が出ても会社は倒産しませんが、資金がショートすると会社は倒産します。
そのような事態を避けるためにも、資金繰りの適正な計画は事業運営に欠かせません。
まず、過去実績から過去分の資金繰り表を作成してみましょう。このような過去の資金繰り表のことをキャッシュフロー計算書といいます。
現金出納帳と預金出納帳を用意して、ひと月ずつ収入と支出を算出してキャッシュフロー計算書を作成します。
・本業以外の資産の売買などで動いたお金を示す「投資活動」によるキャッシュフロー
・借入や返済などで動いたお金を示す「財務活動」によるキャッシュフロー
の3つで構成します。
この3つを合計して、ひと月でお金がどれだけ増減するのかを確認しましょう。
これと同様に未来分のキャッシュフローを算出して、資金繰り表を作成します。
作成しておいた損益計算書を基にして、その増減を確認して事業計画を立てていきます。
つまり最終的に事業計画とは、この資金繰りをいかに組み立てていくかということであると言えるのです。