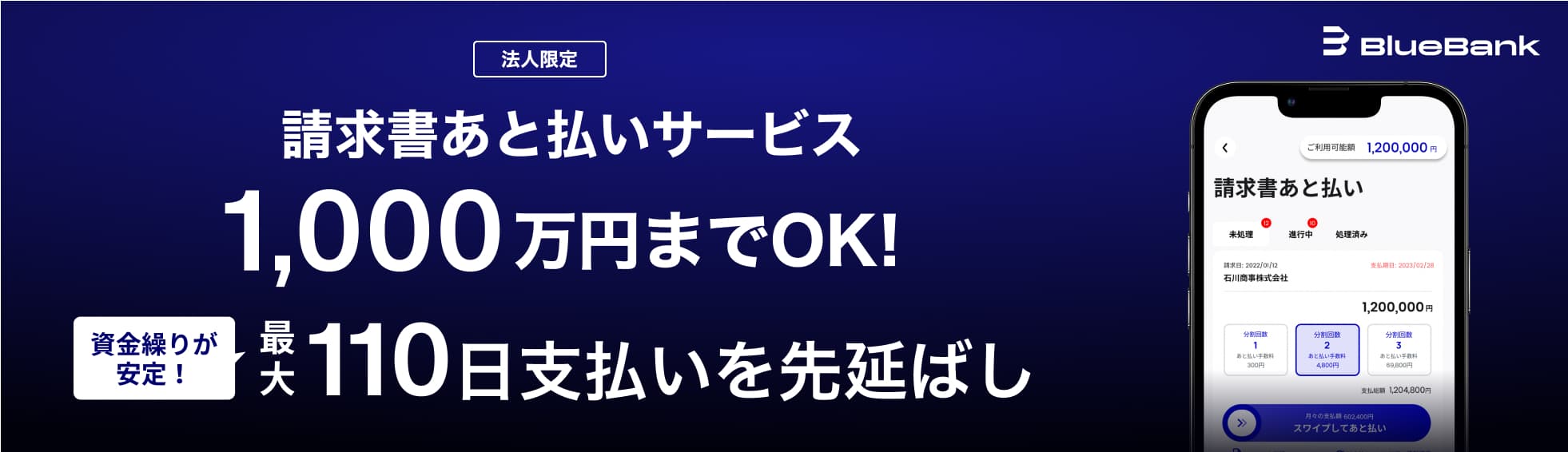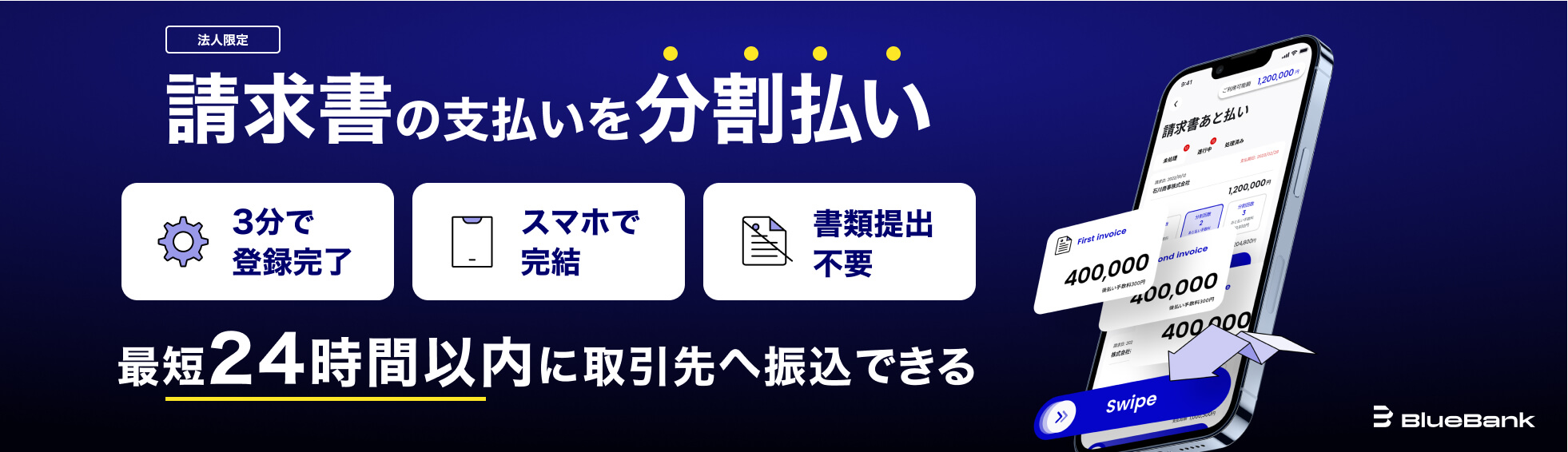売上予測とは、過去のデータや市場動向、成長率に基づいて、売上を予測することをいいます。
銀行をはじめとした金融機関からの融資を検討する際には、事業計画書が作成が必要ですが、その事業計画書の核となるのは何と言っても収支の計画ですが、その中でも一番重要になるのが「売上予測」です。
この記事では、融資獲得に向けた説得力のある事業計画書を作成するための、売上予測の考え方・作成方法について詳しく解説いたします。
本記事に興味のある方におすすめの記事
>>>融資を受ける際に事業計画書は財務計画で決まる!財務計画書の作成方法
なぜ融資の際に事業計画書の売上予測が重要なのか?
収支計画の中にはあらゆる数字が出てきますが、本事業において「入ってくるお金」というのは原則的に売上のみです。
それ以外の売上原価や家賃や消耗品などの、かかる経費はすべて「出ていくお金」です。
入ってくるお金がなければ、当然出ていくお金を捻出できないので、収支計画を考える上でどれだけ入ってくるのかがすべてのスタートになるわけです。
その売上をどれだけ精密に組み立てて予測できているか、その信頼性が事業計画書全体の信頼性に直結します。
売上予測は事業計画書の要なのです。
売上予測の基本的な考え方
売上予測は、ただ予測で数字を並べれば完成というわけではありません。
その予測を達成していければきちんと事業が回っていく、ということを証明できていなければ、融資に強い事業計画書にはならないのです。
売上予測の基本的な考え方のポイントを順に確認してみましょう。
必要売上高を把握することからスタート
売上予測は、その事業にとって必要な最低限の売上を上回っていることが条件です。
つまり、まずは事業の「損益分岐点売上高」を把握することから始まります。
損益分岐点売上高とは「ちょうど利益が0になる」売上のことです。
売上の増減に影響を受けずに毎月かかる「固定費」と、影響を受けて変動する商品仕入高・原価などの「変動費」の2つを把握して、事業の損益分岐点売上高がいくらになるのか必ず算出しておきましょう。
売上を構成する基本要素
どんな業種にも通用する、売上の考え方の大原則は
になります。
売上予測はこの大原則に当てはまった形で算出されていなければなりません。
損益分岐点売上高を上回るには、客単価と客数をどのように想定するのがよいのか、事業の運営自体の見直しを含めて検討をしていくことになるでしょう。
業種別の算出方法
客単価と客数に加えて、売上を構成する要素は様々に存在し、業種によって異なります。
たとえば飲食店であれば、「回転数」や「月当たりの営業日数」も重要な要素になりますし、スポーツジムなどの月額制の業態であれば、「月額の会費」の他に新規会員にかかる「入会金」などの要素も加わってくることもあるでしょう。
業種によって、考慮するべき要素が異なるため、自社事業の売上予測にはどんな要素を考慮する必要があるのか見極めが必要です。
売上予測の算出方法
売上予測の考え方について理解が出来たら、実際に予測の数値を算出してみます。気を付けるべきポイントと共にその方法を確認しましょう。
初月の収支のとらえ方
事業がスタートした直後から、十分な顧客数の獲得が出来ている事業は多くないでしょう。事業が軌道に乗るまでの準備運動のような期間を必ず設けることになります。
十分な売上が見込めないまま、固定費などの支出は当たり前に払わなければならないので、初月から収支は赤字でスタートする可能性が高いと言えます。
逆に、それを想定せずに十分な資金を用意できていないと事業が回らなくなってしまいますので、資金繰り計画と連動して考える必要があります。
黒字を達成するまでの期間
赤字状態で事業がスタートすることを想定したとして、どのぐらいから黒字になるのを目指すべきなのでしょうか。
その目安は、一年以内です。
早いうちから黒字にできれば言うことはありませんが、業種によっては軌道に乗るまでにどうしても時間が必要なものもあるでしょう。
それでも一年以内には黒字に転換する売上予測になっていなければなりません。
このラインをクリアできているかどうかで、融資担当者からの事業計画書の評価も変わります。融資の可否に大きく影響してくるでしょう。
2つの算出方法
実際に売上予測を算出する方法には、「トップダウン」と「ボトムアップ」の2種類があります。
トップダウンは、市場の規模や自社のシェア率を予測して売上高を算出する方法で、市場が成熟する前に多く使用されます。
ボトムアップは、既存顧客の動向データや新規顧客の可能性を考慮して売上高を算出する方法で、成熟期に入って実態データが十分に取れるようになった市場で多く使用されます。
トップダウンは実際の売上とかけ離れてしまうことも少なくないので、まずはボトムアップを意識して売上予測を立てるのがよいでしょう。
つまり、自社で蓄積している既存データ・市場で既に確立されたデータを基盤とすることで、説得力の高い計画にすることができます。
・既存顧客単価✕人数
・過去の実績✕成長率
やりがちな売上予測!注意しておくべき点
事業者が売上予測をする上で、ついやってしまいがちな注意点があります。融資担当者が事業計画書を評価する上でもとても大事なポイントです。
代表的なものを2つ見てみましょう。
根拠となるデータがない
希望観測的な売上予測になっていて、その根拠を示すデータがないというのが一番陥りがちな注意点です。
「これぐらいは売りたいから」
「実力には自信があるので顧客がついてくるはずだから」
このような「ただの願望」での売上予測では、説得力が非常に弱くなってしまいます。
融資担当者も評価はしてくれないでしょう。
市場の既存データ、自社の過去データなどその計算の根拠となる資料を踏まえて、ボトムアップでの数字を算出するようにしましょう。
商品・サービスごとに売上が分かれていない
複数の商品・サービスを展開しているにも関わらず、売上予測が合算で算出されていることがあります。
これでは売上予測が詰め切れていないと判断せざるをえません。
商品・サービス毎に「客単価」×「客数」の予測を示し、その合計として目標となる売上に達している必要があります。
個別に算出根拠となるデータを準備し、客観的に判断のしやすい売上予測にしましょう。
資金のやりくりの仕方はこちらの記事がおすすめです
>>>資金繰り表の作り方!その書き方や活かし方をわかりやすく解説します
まとめ
融資獲得に強い事業計画書に仕上げるためには、明確な売上予測が立っていることは必要不可欠です。
売上予測、収支計画、資金繰り計画、と全ての数値計画が連動した事業計画書になっていることでその説得力を高め、融資獲得へ近づけていきましょう。