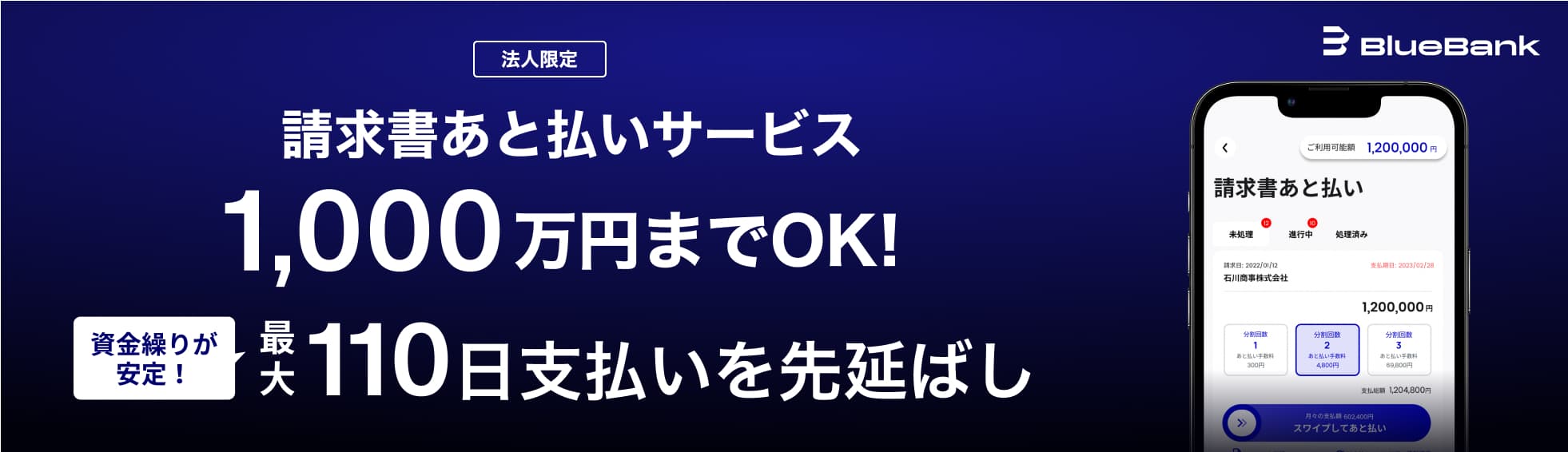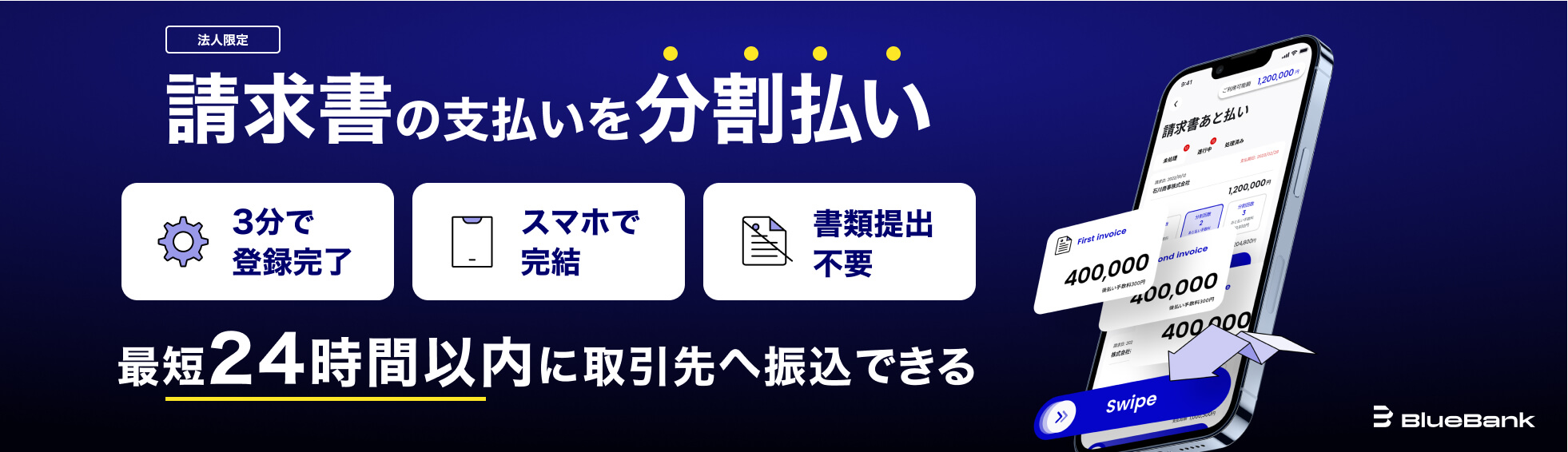金融機関から融資を受けようとする際には、過去の決算書とともにこれからの事業展開を示した事業計画書が必要です。
この事業計画書の仕上がりこそが、融資の可否に大きく影響します。
「融資を受けやすい事業計画書」とはどのようなものなのでしょうか。
それは、ポイントが一目でわかる「キレイな事業計画書」のことです。
キレイな事業計画書に記載されているポイントとは何か、そのポイントをどのように押さえて作成すればよいのか、についてこの記事では詳しく解説いたします。
銀行の融資担当者が注目するポイント

事業計画書を手に、銀行の融資担当者が注目するポイントは、
・資金を何に使うか
・返済ができるかどうか
という点です。
後者の返済できるかどうか、つまり返済能力がある事業者なのかという点は、特に大事だと言えます。
貸したお金が返ってこないという状態を、銀行は最も嫌います。
返済ができることが証明された事業計画書である必要があるのです。
融資担当者は、過去の三期分の決算書と事業計画書をまず見ます。
・損益計算書
・貸借対照表
・キャッシュフロー計算書
の各数値を確認し、主にここから返済能力を判断しているのです。
具体的にはどういう指標で判断をしているのでしょうか。
次項でポイントを詳しく見てみましょう。
返済能力の基準:債務償還年数

返済ができるかどうかを判断する一つの指標として「債務償還年数」があります。
借入金を何年で完済できるかを示した指標であり、代表的な計算式は下記の通りです。
| ・債務償還年数
=(有利子負債残高 - 現預金 - 正常運転資金)÷(純利益 + 減価償却費) |
債務償還年数のひとつの基準として押さえておきたい区切りが「10年」です。
数値が10年以内になるならば、融資担当者の評価は良いでしょう。
逆に10年を超えるようであれば、それだけで途端に融資を受けられる確率も減ります。
業種による例外もあり、初期投資に多額の資金がかかる不動産業のような業種の場合、この基準が30年になる、ということもあります。
このように業種によって変動することは考えられますが、一般的には10年がひとつ大事な基準となるので、意識した事業計画書に仕上げる必要があるでしょう。
債務償還年数を意識した数値計画を立てる際の注意点
債務償還年数を10年以内に収めることを優先するがあまり、表面の数字だけを意識した現実性のない計画書にしてしまっては意味がありません。
特にやってしまいがちなのが
・願望だけで客観性のない数値の売上になっている
・過剰な経費削減案になっている
などです。
市場の動向、営業方法のブラッシュアップ、組織マネジメントなどの一切を無視した売上予算では意味を成しません。
経費についても、過剰に削減してしまうと従業員のモチベーション低下を招くことがあり、結果的に売上の低下につながりかねないので、適度にゆとりを持った数値設定でなければなりません。
実態の伴った数値計画になっている必要があるのです。
その数値計画はどのように作成すればいいのかについては、次項で詳しく見てみましょう。
損益分岐点から逆算して数値計画を作る

返済を滞りなく実施していくには、利益を出し続けることが必要です。
その利益を出すための判断基準を適正に持ち、数値計画を立てることが不可欠となります。
利益の出る数値計画は、「損益分岐点」から逆算して立てていくことが基本です。
損益分岐点の基本的な定義は「利益が0になるところ」、つまり売上と費用が等しい状態のことです。
計算式は下記の通りです。
| ・損益分岐点 = 固定費 ÷(1-(変動費 ÷ 売上高 )) |
「変動費 ÷ 売上高」の値は「変動費率」と呼び、
「1- 変動費率」の値は「限界利益率」と呼ぶので
| ・損益分岐点 = 固定費 ÷(1- 変動費率)= 固定費 ÷ 限界利益率 |
と表すこともできます。
これを基準として必要な売上がいくらか、などを判断していくことになります。
たとえば、固定費が100万円、限界利益率が20%だとすると
損益分岐点 = 100 ÷ 0.2 = 500万円
となります。
営業利益の目標を30万円にしたい場合、それにかかる変動費も考えて
売上 = 30万円 ÷ 0.2 = 150万円
これに先ほどの500万円を加算して、650万円という金額が算出されます。
これが目標とする営業利益30万円を確保するための、必要売上高ということになります。
このように、自社の事業における損益分岐点がどこにあるのかを正しく把握することから、数値計画の立案は始まります。
損益分岐点が下がると利益が出やすい
損益分岐点が下がれば、売上高が変わらなくても出せる利益が増えます。
黒字体質であるためにも、下げる方法はないか検討が必要でしょう。
方法は主に二つあります。
・固定費を下げること
・変動費を下げること
になります。
固定費削減については、債務償還年数の項目で経費削減について述べたように、過剰に削減すればよいわけではないので注意が必要です。
変動費削減については、仕入方法を見直しての仕入原価削減、製造方法を見直しての製造原価削減、営業方法や販売ルートを見直しての販売費削減などを図ることで見込めるでしょう。
損益分岐点を考える上での注意点
計算式にも示した通り、損益分岐点を算出するには費用を「固定費」と「変動費」に適切に分類していることが前提になります。
しかし、分類が難しい場合もあります。
人件費であれば固定給と残業代が入っていますし、水道光熱費も固定の基本料と使った量に応じた変動の使用料とが含まれるでしょう。
また、売上見込みの増大に伴って生産設備や人員の増加が必要となり、固定費が増えることになれば、損益分岐点もずれてきてしまいます。
このように、費用の分類の方法や状況の変化によって算出される損益分岐点の数値も変わってきますので、都度適切な見極めが必要になるので注意しましょう。
まとめ キレイな事業計画書の作り方とは
返済がしっかりとできることがわかる、返済分を見込んで利益を上げられる数値計画が立っている、それが一目でわかる明確な事業計画書のことを「キレイな事業計画書」と呼ぶことができます。
キレイな事業計画書は、そのまま「融資を受けやすい事業計画書」になるのです。
融資担当者が思わず頷いてしまうような、ポイントが明確なキレイな事業計画書の作成に臨んでみましょう。