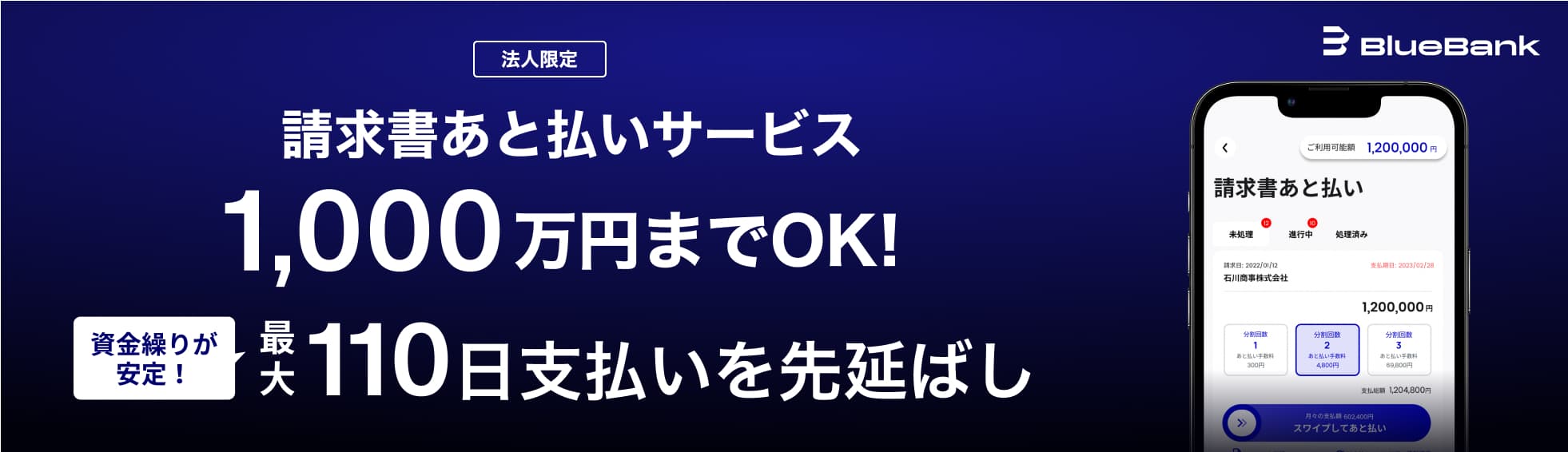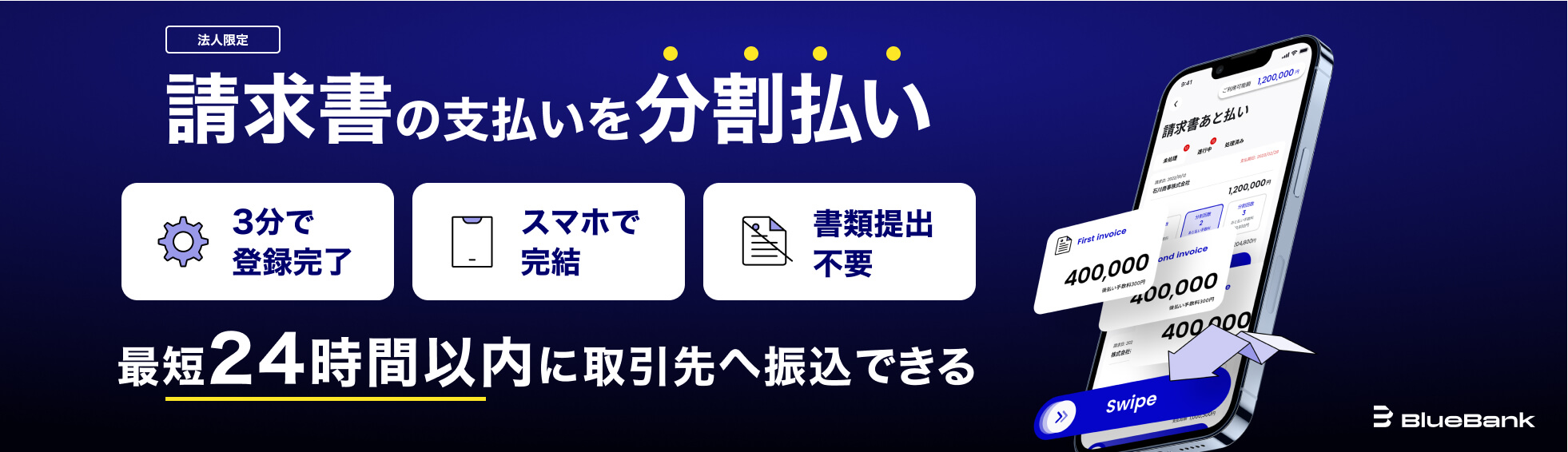事業計画書には決まったフォーマットが無いので、100社の会社があれば100通りの事業計画書の形がそこには存在します。
「じゃあ、好きなように作ってしまおう」
「ネットで適当なフォーマット拾えば十分か」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これでは大事な要素を記載し損ねてしまう可能性があります。
外すべきではない重要な項目は存在するのです。
その主要項目とそれぞれの考え方・とらえ方についての理解を深め、完璧な計画書を目指して作成していきましょう。
■事業計画書の項目ではずせない重要な5項目とは?

事業計画書には、明確な事業予算を記載することが欠かせません。
数字で計画を表現することが求められるのです。
その事業予算の中で、はずせない主要な項目は、
| ・売上高
・粗利益 ・固定費 ・変動費 ・損益分岐点 |
の5点です。
この中でも5つ目の損益分岐点については、正しく理解されている方は案外多くはないものです。
売上高、粗利益、固定費、変動費、この4つを正しく把握した上で初めて算出できるのが損益分岐点であり、事業予算を検討する際の重要なひとつの基点となります。
それでは各項目を詳しく見てみましょう。
■売上高
商品やサービスを提供し、発生した売上の合計が「売上高」です。
事業予算の検討は、まず売上高を予測することから始まります。
| ①商品別、サービス別に売上を分けて、1か月分の売上高を作成する
②12か月分の売上高を算出し、1期の合計売上高を作成する ③それを3~5期分作成する |
手順としてはこれだけのことですが、ポイントとなるのは「何を元にして算出した数字なのか」という点です。
根拠のない希望的観測で作成してしまっては絶対にいけません。
既に過去の実績データがあるのであれば、そのデータを元に作成する必要があります。
・顧客への販促活動を前年比〇〇%増で実施する
・その結果、売上見込みを前年比△△%で算出する
など計算根拠を明確に示せるようにしましょう。
これから創業する場合や新規サービスに取り組む場合は、既存のマーケットを調査することから始めます。
他社の過去データや市場データを取得し、その数字を基にして予測の売上高を算出します。
予算はあくまでも予測での数字でしかないので確実なものではありませんが、その計算の根拠がない売上予算は評価の対象外となってしまう可能性が高いので注意しましょう。
■粗利益
粗利益とは、売上高から売上原価を差し引いた利益のことで、売上総利益とも呼びます。
この粗利益を見るときは「粗利益率(粗利率)」に注目しましょう。
売上高に対してどれだけの粗利益が上がったかを示す指標で、%で表します。
例えば、同業種において単月に同じ額の粗利益を挙げた2社があるとします。
・A社 売上100万、原価80万、粗利益20万
・B社 売上50万、原価30万、粗利益20万
このような結果の場合、どちらの方が実力がある会社だといえるのでしょうか。
粗利益率を計算してみると、A社20%、B社40%になり、B社の方がより効率的に粗利益を上げられていることがわかります。
その結果、B社の方が実力がある会社と評価されるわけです。
業種によって平均となる粗利益率は異なりますが、
・売上に対してどれぐらいの割合で利益をとれている事業なのか
・粗利益率を上げるにはどんな方法が考えられるか
という視点で自社の事業を見直してみましょう。
■固定費
固定費とは、売上がどれだけ上がったかに関わらず発生する一定額の費用のことで、不変費とも呼ばれます。
具体的には、人件費、地代家賃、水道光熱費、通信費、リース料、広告宣伝費などが固定費として分類されます。
固定費に注目が集まるのは、赤字が続いて事業の見直しを図る必要がある時です。
真っ先にテコ入れ先として挙げられ、いかに削減するかを検討することになります。
具体的な削減方法としては
・家賃価格を交渉して値下げを図る
・水道光熱費、通信費の契約プランの見直しをする
などがまず挙がります。
くれぐれも注意をしなければならないのは、安易な削減を図らないことです。
なぜ必要なのか、どの程度までする必要があるのか、社員間で情報共有することはかかせません。
固定費の削減には「社員のモチベーション低下」を引き起こす可能性を含んでいるからです。
人件費の削減に乗り出す、などはその最たるものでしょう。
「無駄のない効率的な方法を選択する」という意識で固定費を最適化することが大切です。
■変動費
変動費とは、固定費とは違って売上の増減で変動する費用のことで、可変費とも呼ばれます。
具体的には、原材料費、仕入原価、販売手数料、外注費などが変動費として分類されます。
固定費に続いて、変動費もよく削減を検討される項目です。
具体的な削減方法としては、
・大量仕入れや現金支払いなどで値下げを図る
・外注先に価格交渉して値下げを図る
などでしょう。
これに伴っては、大量仕入れに伴う在庫スペースの確保や、支払いサイクルが変わることによる資金繰りなど、合わせて検討が必要な点が挙がってきます。
外注先の値下げを実施するにあたっては、クオリティの低下を招く恐れもあります。
それが売上の低下につながるようでは本末転倒ですから、慎重な見極めが必要でしょう。
変動費は、提供する商品・サービスの質、売上高に直接影響が出てくる項目ですので、事業全体を見つめた適切な設定が必要でしょう。
■損益分岐点
最後にようやく、損益分岐点についてです。
損益分岐点とは、営業利益がちょうど0になる売上高のことです。
営業利益を簡単な計算式で表すと、
| ・売上高 - 売上原価 = 粗利益(売上総利益)
・粗利益 - 販売費及び一般管理費(販管費) = 営業利益 |
となります。
この営業利益が0ということは、「売上と費用が等しい」状態であるということです。
事業予算を組む時は、この損益分岐点となる売上高はいくらかを把握することから始まります。
この損益分岐点は、低いほど良いとされます。
同じ売上を上げる場合、損益分岐点が低い方が利益が大きいわけですから当然のことです。
では、損益分岐点はどうやって下げればいいのでしょうか?
前項までで述べてきた
・固定費を削減すること
・変動費を削減すること
この2つが主な方法です。
各項目の注意点は前述の通りですので、事業にとって適切といえるレベルでの数値設定に細心の注意を図り、損益分岐点を下げられるようにしましょう。
■まとめ
事業計画書を作成するときは、「売上高・粗利益・固定費・変動費・損益分岐点」の5項目に注意を払いながら、必ず事業計画書に記載をしましょう。
しっかりと利益を生み出せるビジネスモデルを計画していることが証明され、金融機関の融資審査にも強い事業計画書へ近づいていくことでしょう。